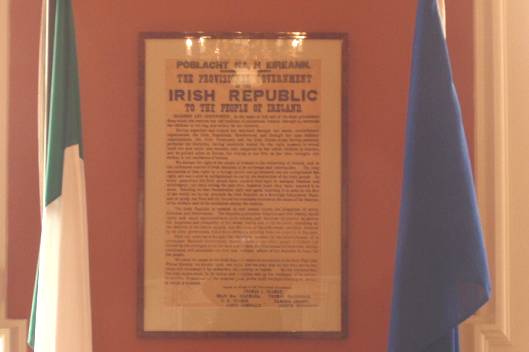|
アイルランド銀行旧本館とトリニティ・カレッジのあいだの道をそのまま南に進むとグラフトン通り(Grafton Street)へとつづきます。300mくらいにわたって歩行者専用道になっており、各種のショップが両側に立ち並ぶ一大ショッピング・ゾーン。東京でいったらどこになるのかなあ、銀座ほど巨大ではないし、新宿のように猥雑ではない。ミシュランのガイドブックではchicという形容詞で表現されています。上品でしゃれた感じということでしょうか。欧州の各都市では景観保全のため条例などで建物の外観を規制することが多く、そのおかげで上品な雰囲気を楽しむことができますが、ここもそうなのでしょうかね(パリなんか最大級に厳しいらしいです。といいつつ非常にアジア的な新宿を愛好して、もう20年以上も住んでいる私 笑)。水曜の午前中なのですがもうかなりの人出があります。
 
 グラフトン通り グラフトン通り
通り沿いにブラウン・トーマス(Brown
Thomas)という、まさにシックなデパートがありました。ここのメンズは地下1階にありました。おお、カジュアル部門も品のいいブランドものばかりでけっこういい値段。欧州のデパートやショッピングビルに入れば自分用のネクタイを物色するのが恒例になっています。ディスプレイの仕方も上品で、パリでいえばラファイエット流ではなくプランタン流。数年前までは色合いの地味なものを見ても「おじさん風だなあ」と思って回避することが多かったのだけど、年齢のせいか最近はそういうのが嫌いでなくなってきました。それなりのおとななので、勝負ネクタイとしてはいいものを身につけたいものです。丁寧な言葉遣いの女性店員が寄ってきてガイドしてくれます。こちらが目に留めた品物のいいところを褒め、それに近い品も紹介するというきわめてスマートな対応で感心しますね。アイルランドのカントリー・カラーは緑なので、緑系のものにしようかな。というので、前日にパリのプランタンでけっこういいやつを2本買ったばかりなのですがここでも€120のを選んで包んでもらいました。買い物も年々インフレ化しています。ちなみにアイルランド共和国の消費税率は23%なので本体価格は€100を切るくらいですね。VISAでチェックしたら、「空港でリファンド(免税手続き)できますのでこちらをおもちください」と、ブラウン・トーマスの封筒に入った手続き書類をくれました。消費税(VAT 付加価値税)の一部を後日返還してくれるしくみです。へえ、フランスは1ヵ所で€175以上買わないと免税対象にならず、ゆえにこれまでしたことがなかったのですが(同行した母の買い物に付き合って手続きしたことはあります)、アイルランドはどうなんでしょうか。あとでネットで見たのですがよくわかりませんでした。ところで、Where can I submit my VAT refund form? と題されたインストラクションが封筒に書いてあるのですが、ダブリン空港での手続きに関してしか情報がありません。この制度は非EU圏に出て行く人に適用されますので、本来は最後にEUを出る空港ないし駅・港で専用ポストに投函するものなのだけど、ロンドン・ヒースロー空港で処理してもらえるものかどうか、いまのところ不明。もしわからなければ帰国後にエアメールで送ればいいか。もともとリファンドなんて期待せずに買い物したのだから、ダメでも別にいいです。町歩きをはじめたばかりなのにもうショッピングというのも何ですが、また同じところに来るともかぎらず、同じ品に出会えるわけでもないので、お土産とか自分用のものを買いたいときはこれと思ったタイミングで買うのがベストです。ネクタイなんて軽いものですからね!
各都市の目抜き通りと同様に、グラフトン通りには衣料品、宝飾店、スーベニア・ショップなどが目立ちます。本格的なレストランなどはなく(おそらく横道にあるのでしょう)ファストフードの類のみがあるというのも一般的な傾向のとおり。この通りの南端(終点)付近に小さなチョコレート屋さんがありました。欧州のお土産といえばチョコレートと決まっており(でもないか)、ダブリンのものなんてめずらしいからいいのではないかな。気に入った品を数点買っていきましょう(好評でした)。もっともこのお店はテイク・アウェイのコーヒー屋さんとして機能しているらしく、入ってくるお客の大半は飲み物を求める地元の若者でした。
  セント・スティーヴンス・グリーン セント・スティーヴンス・グリーン
グラフトン大通りの終点は、都市型公園として知られるセント・スティーヴンス・グリーン(Saint Stephen’s Green)のメインゲートに接しています。お天気がよくほぼ無風のお昼前とあって、高齢者や幼児づれの夫婦などがたくさんいて憩っていますね。私も都市型公園というのは大好きなので、ベンチに腰かけてしばしゆるゆる。地図を取り出して、これから数時間のだいたいの方向性を考えておきます。ぜひ何を見たいとかいうものもないので、気分とかその場の勢いによっていくらでも変更・修正してしまうのはいつものとおりです。まだ市街地の一角をまっすぐ歩いてきただけで全体的な傾向はわかりませんが、ダブリンは思いのほか大都会ですから、昼食を取りはぐれるとかいうこともなさそうですね。
正午ころグリーンを切り上げ、ドーソン通り(Dawson Street)なる南北の道に入り込みました。小ぎれいなレストランやカフェが並んでいます。道沿いに正面をおしゃれに縁取ったきれいな建物があり、マンション・ハウス(Mansion House)とのことです。いま調べてみたら、1715年に建てられたダブリン市長(Lord
Mayor of Dublin)の公邸で、現役だそうです。その先に、今度は三角形の屋根を載せた教会とおぼしき建物。こちらは聖アン教会(St.Ann’s Church)で、ファサードなど現状の主要な部分は19世紀後半のものです。実際にこれを見たときには「古そうな教会だなあ」と思ったくらいでとくに関心をもたなかったのだけれど、うかつですよね。アイルランド議会、トリニティ・カレッジ、ダブリン市長公邸とあるいわば中枢地区に建てられているのだから、これが民衆のための寺院とはいいがたいものだったことを発想すべきでした。聖アン教会は、アイルランド共和国のマジョリティであるカトリックではなくて、アイルランド国教会(Church of Ireland)の教会なのでした。
 
(左)マンション・ハウス (右)聖アン教会
12世紀後半にイングランド王がアイルランドの宗主権を獲得したものの、その後に英仏百年戦争(1337〜1453年)、イングランドのバラ戦争(1455〜85年)などもあって、アイルランドの相対的自律の時期がつづきました。早くに入植したイングランド系ないしノルマン-フレンチ系の勢力もやがて在地勢力化し、15世紀ころにはゲール語がむしろ全島で共通に話されるほどに普及するなど、アイルランドの独自性が強まります(前掲『物語
アイルランドの歴史』、pp.80-85)。しかし15世紀末にテューダー家がイングランドの王位を継承すると事態は急変しました。イングランド王ヘンリー8世(Henry VIII 在位1509〜47年)は、新しい恋人と再婚したいというので王妃との離婚を図り、これがローマ教皇に許されなかったことから独自の宗教(イングランド国教会 Church of England)を立てて宗教改革をはじめた、という文脈で知られます。話の本筋がどこにあるのかは別にして、彼の下で国王主導によるイングランド独自の宗教改革が進行したことは確かでしょう。アイルランドに対しては、在地の有力者を通じてイングランドの利益を浸透させる間接統治が常態でしたが、宗教改革に反発するアイルランド貴族たちはヘンリーへの反抗を強めました。アイルランドは古代末期いらい敬虔なカトリック信仰の地であるので、宗教的な動機もありましょうが、おそらくはヘンリー8世の絶対王政化への危惧という世俗政治のことが背景にあったと思われます。
首長法(Act of Supremacy イングランド王が教会の最上位にあることを規定する法で、国教会成立の契機となった)が成立した翌1534年、アイルランドの最有力者で現地におけるイングランド王の総督でもあったフィッツジェラルド親子が反乱を起こすと、ヘンリー8世は大軍を送って容赦なくこれを鎮圧し、アイルランドを強硬に支配して反抗の芽を摘み取ろうとします。1541年、アイルランド議会は、アイルランドの教会において宗教改革をおこないアイルランド国教会を立てること、その首長にヘンリー8世を戴くことを決議しました。国教会の内容やしくみはイングランドのそれとほぼ同じですので、アイルランド国教会の首長はすなわちアイルランド王(King of Ireland)ということになります。こうしてヘンリー8世はイングランド王兼アイルランド王ということになり、以後その地位は歴代のイングランド王に引き継がれました。もちろん、それぞれ議会をもつ別の国であり王が共通であるという同君連合のかたちを採ります。しかし経緯からしてイングランドの圧倒的優位は明白でした。
ヘンリー8世のあと、夭折したエドワード6世をはさんでその姉でカトリックのメアリー1世が即位。アイルランドのカトリックにとっては小休止の時間となりましたが、次のエリザベス1世(Elizabeth I 在位1558〜1603年)の時代にはイングランドによる支配強化が急速に進むことになりました。国教会の制度と信仰を復活させ、父がはじめた絶対王政路線をより力強く進めます。エリザベス1世といえばスペインのフェリペ2世のライバルとして知られます。スペインの強大化を阻むため、その支配地であったネーデルラントの新教徒たちを支援して独立につなげ、1588年にはイングランド侵攻を図った無敵艦隊を海上で撃破して力関係を逆転させました。エリザベス自身はアイルランドへの強硬な介入を必ずしも望んでいなかったようですが、スペインとの戦争に注力していたため現地アイルランドの出先機関やそこに利害をもつイングランド人は本国を差し置いて土地の接収や強引な入植を進めたのです。また、カトリックのアイルランド人をスペインが焚きつけてイングランドへの反抗を煽ったことも、強い警戒心につながりました。結局、女王最晩年の1601年にアイルランドの在地勢力とスペインが結んで大規模な反乱を起こしたのを機に、イングランドは直接的な軍事介入に踏み切り、スペイン軍を追い出し、在地勢力をことごとく粉砕して教会を含むカトリックの土地所有を認めない苛烈な方針で臨むことになります。1603年にエリザベスが死去すると、スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王兼アイルランド王ジェームズ1世(James I 在位1603〜25年)として即位し、3つの国が同君連合として結びつきました。
 
 
かつては国教会やイングランドの威を借りた人たちが、選挙権・被選挙権すら奪われて商工業に専心することになったダブリンの市民ににらみを利かせたのが、聖アン教会の周辺なのでしょう。トリニティ・カレッジは前述のようにエリザベスが創立した国教会系の大学でしたし、アイルランド議会もヘンリー・エリザベス父娘の介入後は国教会の府と化しました。私は聖アン教会を背にグラフトン通りに戻り、今度はその西側のエリアに入り込みました。狭い路地や商店街がつづく旧市街のようです。小規模のショッピングセンターを冷やかし、各種ショップのショーウィンドウをのぞき込むなどしていつもの町歩き。タワーレコードがあるけど、月内有効の割引券はここでは使えまいな(ていうか、好みのアーチストのCDをダブリンで売っているはずはないし、そもそも欧州のCDを日本のプレイヤーにかけても音は鳴りません)。
小さな商店や飲食店が並ぶところを通り抜けると、尖塔が目立つ小さな教会が現れました。いま調べたらここは聖アンドリュース教会(St.Andrew’s Church)で、やはりアイルランド国教会の施設ですが、現在はツーリスト・インフォメーション(観光案内所)が入居していて“Discover Ireland”と掲げてありました。もとより発見するのにやぶさかではありません(笑)。
 
これから向かおうとしているのは、ここからリフィ川方向に少し下ったところにあるテンプル・バー(Temple Bar)と呼ばれるエリア。ダブリン関係のガイドブックや書籍ではたいていおすすめエリアになっています。場末になりかかっていたところを1990年代に再生したもので、文化発信地区として発展しつつあるということらしい(芸術文化や言語などの専門学校が多いので)。飲食店も密集しているそうだから、ことによってはランチを食べられるかもね。

 
(左)観光パブの呼び込みをしている (右)マクドナルドなのだけど景観に配慮したのか赤色もMマークもない・・・
 こちらスターバックスも、ちょっとだけおとなしめ? こちらスターバックスも、ちょっとだけおとなしめ?
そのテンプル・バーに入り込んでみると、なるほど石畳をしつらえた道の両側にさまざまな飲食店などが並んでいます。あまりに観光地然としたスポットは評価が分かれるところですが、そんなことをいえば浅草の仲見世なんて成立しなくなるし、コンセプトがはっきりしているのでいいのではないですかね。再開発のお手本のような場所ではあります。12時半を過ぎていますが思ったほどの人通りはありません。おそらく夜になると賑わうのでしょう。何人かの呼び込みさんがいて、バインダーに綴じたメニューを見せ、観光レストランないしパブと思われる店への誘導を図っています。様子を見ていると「そこを進んで、そっちに曲がって・・・」みたいな指示だったので、裏道など場所的に不利なお店が雇っているのかもしれません。呼び込みさんだらけだった1年前のリジュボーアの飲食店街を思い出しました。
 
(左)ミレニアム・ブリッジから下流側を望む 奥に旧税関のドームが見える (右)テンプル・バーの渋い路地
あからさまな観光レストランは嫌なので、ぼちぼち歩きながら探すことにして、路地や横道にも入ってみます。どことなく裏原宿っぽくもあり、新宿のゴールデン街っぽくもあり、横浜中華街の香港路っぽくもあり。リフィ川の右岸に出てひと呼吸してからまた戻り、渋めのパブを選んで入ってみました。パブの当たり外れなんて外観でわかるものでもないし、入ってみてもよくわからん(苦笑)。ともかくも、アイルランドといえばイングランド同様にパブなので、パブめしを食しておきませんとね。店内の先客は7〜8人くらいで、窓際では地元の人らしき中年の夫婦がゆったりとビールを飲んでいます。キャリーバッグをもったキャリアウーマンさんとか、昼飲みが常態化しているとおぼしき初老のおっちゃんとか。カウンターには十数種類のビアサーバーが並んでいました。おおこれは選びがいがありますね。20歳くらいのさわやかなお嬢さんがきびきび働いています。スタウトはどれですかと訊ねたら、ここからここまでですと教えてくれました。ここでもギネスは禁欲?して、オハラ(O’hara’s)の1パイントを発注。それと、Slow Cooked Irish Stewなる品を頼みます。ゆっくり調理されたアイルランド風のシチューって何だろ? 「今日はラムではなくビーフなのですが、よろしいですか?」というので、もともと何だか知らないのに、イエスと答えておきました。パブの作法としては、カウンターで先に精算して飲み物を席にもっていき、フードはあとからもってきてもらうというのが普通なのですが、お嬢さんは「チェックはあとで結構です。お席でお待ちください」と。
 
  パブで昼食♪ パブで昼食♪
中年夫婦の隣、明るい窓に面したところのスツールに腰かけて、まずは褐色のビールを口にします。初めての都市で飲むビールは実に美味いですねとか、男は黙って1パイントだとか、この西欧あちらこちらのあちらこちらで擦り切れるほど使ったフレーズしか思い浮かびません(汗)。美味いものは美味いのだから文句あるか。5分くらいしてから「シチュー」が運ばれました。あ、これは大半の日本人が想像する「ビーフシチュー」じゃないですか。肉がメインではなくスープをスプーンで飲むというような。真ん中に、アイスクリーム状にしたマッシュポテトが2つサーブされており、これを突き崩してソースと絡めると、なかなかよい味です。肉も思いのほかごろごろ入っている。3日前の日曜夜にパリで猪肉のシチューを食しており、それも似たような見た目と味でしたが、こちら(アイリッシュ)のほうがより気に入りました。野菜スープがベースになっているんじゃないかなあ。ビールが€5.40、シチューが€9.95で〆て€15.35。ごちそうさまでした。
  テンプル・バーと専門学校 テンプル・バーと専門学校
  シティ・ホール シティ・ホール
満腹したところで町歩きを再開しませう。テンプル・バー界隈をぐねぐね歩いて、大通りに戻ってきました。カレッジ・グリーン(College Green)、デイム通り(Dame Street)、エドワード卿通り(Lord
Edward Street)と細切れに呼称が替わるものの、トリニティ・カレッジおよびアイルランド銀行旧本館の前からまっすぐ西に伸びてくる幹線道路です。戻ったところにシティ・ホール(Halla na Cathrach / City Hall ダブリン市役所)の立派な建物がありました。トーマス・クーレイが設計して1779年に完成したネオ・クラシック様式の建物で、当初は王立取引所として用いられていたものを、1852年にダブリン市が引き取って庁舎にしたということです。
シティ・ホールはそのままダブリン城(Caisleán Átha Cliath / Dublin Castle)と敷地続きになっています。午後のメインはこのお城の見学ということにしましょう。このあたりは市内随一の高さのあるところで、都市ダブリンができて以来その政治的・軍事的中心でした。ダブリンを最初に建設したのは北欧から侵入したヴァイキングで、841年のことだったとされます。1169年、今度は3年前にフランスからやってきてイングランドの制圧に成功したノルマン人たちが侵攻、翌年にダブリンを占領しました(日本の「世界史」だとヴァイキングとノルマンの境目がはっきりしないのですが、アイルランドやブリテンでノルマンといえばフランス系の人たちを指します)。ただ、この場所に「ダブリン城」を建設させたのはイングランド・プランタジュネット朝の3代目、ジョン欠地王(John
“the Lackland” 在位1199〜1216年)でした。前述のように、中世後期のアイルランドはイングランドの宗主権を認めながら全般的には自律的であったと考えられますが、ダブリン周辺はイングランド系の入植が進み、いわばイングランドの橋頭堡のような地であったわけです。以来ダブリン城はこの島におけるイングランドの総督府としての機能を果たし、20世紀にいたりました。高台から町を見下ろす軍事的要衝であったことはいうまでもありません(“Dublin Castle: Caisleán Átha Cliath” ダブリン城のパンフレットを参照)。
 「お城通り」 「お城通り」
シティ・ホールからお城の入口(コーク・ヒル門 Corke
Hill Gate)まではものの20秒もかからないで行けます。が、ホールを最前線として、少しだけ標高の高いところにあるお城の攻撃を試みた人たちがありました。まさに隣接する要衝を攻略し、反乱の実を上げようとしたわけです。1916年4月24日、復活祭の月曜朝に起こったイースター蜂起(Éirí Amach na Cásca / Easter Rising)でのことでした。1801年にグレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立して以降、アイルランドの独立をめざす動きはさまざまなかたちで展開されますが、ロンドンの議会での立法措置などを通じて漸進的に独立を勝ち取っていこうとするか、武装蜂起によって一挙に独立をめざすかといった路線対立が起こりました。後者の一派は第一次大戦で連合王国が大陸に派兵している間をねらって一斉蜂起するという計画に走ります。しかし、ドイツとの連絡が連合王国側に傍受されたり、計画が未然に露見して中途半端な動員しかできなかったりと、不十分なままの決起になってしまいました。市民たちの義勇兵はシティ・ホールを奪取して、まさに敵の総本山に牙を突きつけるのですが、翌25日には早くも反攻を許し、ホールも奪還されてしまいました。このとき守備兵側は城内で最も高いベルフォード・タワー(Belford Tower)から狙撃をおこなって義勇兵を次々に倒していったといいます(城内の解説板による)。イースター蜂起は1週間ほどで完全に鎮圧され、指導者たちはことごとく処刑されました。戦闘中に瀕死の重傷を負ったジェームズ・コノリー(James Conolly)は、いったん城内に運ばれたのち、銃殺されています。しかし、蜂起自体はこのように不首尾に終わりましたが、「16名の指導者たちの処刑は(略)この国のムードを完全に変えてしまった」(Pocket History of Ireland, p.49)。それはきっと、アイルランド人たちのナショナリズムにいよいよ火をつけたということと、この事件を通して連合王国の支配の現実というものをリアルに実見したことによるのでしょう。
 
(左)ベルフォード・タワー(1761年完成) (右)コーク・ヒル門
お城とはいっても、17世紀に大火事で大半を焼失して、以降はむしろ「宮殿」のようであったといいます(前掲 パンフレット)。たしかに見たところでは小ぶりの宮殿か、政庁とでもいうくらいの建物です。石畳の中庭を通って建物の中に入り、€4.50のチケットを求めました。荷物は無料のロッカーに収めて手ぶらでお通りくださいとのこと。中高年の団体さんに明朗な女性ガイドさんがついて、あれこれと見どころを説明しているので、便乗して聞き耳を立ててみます。ここはイングランド王の代理である総督以下がいたところなので、いわゆる君主の宮殿というよりは、貴族の邸宅の少し豪勢なやつという感じなのでしょう。それでも、部屋の造りも調度品もさすがに見事なものばかりです。
この種の観光施設では当然のことに、主要言語のパンフが用意されていて、私はいつものように英語版とフランス語版を読み比べながらふむふむと思考しています。ワープロ打ちしたA4用紙をホチキス止めしただけではありますが日本語版もありました。「王座の間」(Throne Room)についてはこうあります。「金箔に飾られた見事なシャンデリアは1836年製、アイルランドの国花クローバーとスコットランドのアザミ、イングランドの国花のバラがモチーフであるが、これは1801年の連合法によるグレートブリテンおよびアイルランド連合王国の誕生を記念したものである」(原文ママ)。英文のほうは“with shamrock, thistle and rose motifs, commemorates the 1801
‘Union of Great Britain and Ireland’”とあって、花の名前を並べれば3国の名を付さずともその意味はおのずとわかるということなのでしょうね。英語話者イコールアイルランドないしブリテンの人というわけでもないだろうから、日本語のように丁寧に書くほうがいいとは思いますけど。
  コリドーと階段 コリドーと階段
 「王座の間」 「王座の間」
イースター蜂起に際しては、リフィ左岸のオコンネル通りが司令部となり、義勇兵の一部はセント・スティーヴンス・グリーンに終結して市街地の占拠をめざしたとかいうわけだから、98年前には今日ここまで歩いてきたところの周辺で壮絶なことが起こっていたわけです。
私が先週末に欧州に来てから、地続きである東欧のウクライナが大変まずいことになっています。ロシア寄りの姿勢を打ち出して親EU派の勢力を刺激したヤヌコヴィッチ大統領がついにその座を追われ、行方をくらませました(後日ロシアに亡命と判明)。するとロシアのプーチン政権が軍事介入をちらつかせはじめました。ウクライナ南部、黒海に面したクリミアは、親EUに舵を切ったウクライナ国家からの離脱をめざすのではないかとみられています。EUやアメリカはもちろんウクライナの暫定政権を支援し、クリミアの分離独立を認めないことでしょう。ソチ五輪が終わったばかりなのに何ということか。――ただ、こういうニュースに接すると、ウクライナのことはウクライナ人自身が決めるべきであり、そのウクライナ人が民主主義を尊重する西側に接近するのだからいいことなのではないか、それを妨害するロシアはソ連時代の覇権主義に戻ったのか、などと短絡して考えがちです。この1年指導してきた高校3年生H君のウクライナ史に関する卒論がつい最近完成したのですが、その過程でなじみの薄い東欧の歴史やナショナリズム、現状などについて私もずいぶん勉強しました。簡単にいうと、こういうことです。いま「ウクライナ」と呼んでいる領域には、ウクライナ人もいればロシア人もいてその境界はあいまいです。ウクライナ語とロシア語は7割くらい互換性があって、もう「方言」レベルなのだけど、独立以来ウクライナ語の国語化が進められてきました。が、実際にはロシア語話者のほうが多いらしい(信念から当人がそうと認めないケースも含めて)。ウクライナの歴史はロシアのそれとは違うのだとウクライナの公式の歴史観は語りますが、そもそも国民国家単位の歴史を過去にさかのぼらせることが困難というか無理筋。そして、ウクライナ西部は親EUの傾向が強く東部は親ロシアの傾向が強いけれども全面的にそうだというのではないし、グラデーションもあります。たとえば、7対3くらいの対立事案があるとする。民主主義に従えば3割のほうはがまんするしかありません。民族とか言語などのアイデンティティにかかわるものを含めて。クリミア半島は政治史的な背景によってロシア系住民が多いところなので、当該地域だけの民主主義なら「ロシアに編入」となるに決まっていますよね。ウクライナ全体にまぶすとマイノリティになります。欧米諸国の本音は、いま民族ごとの自立を根拠にした国境変更を認めてしまうと、地球上のあちこちでナショナリズムが燃え上がり、独立闘争が多発するというのを恐れているのです。でも、ロシアはきっとこういうでしょうね。ユーゴスラヴィアに軍事介入して連邦を解体し、コソボの独立を承認して国境変更させたのは誰たちでしたっけ?(日本政府も承認しました)
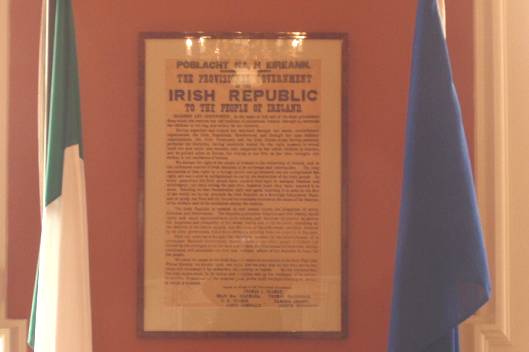
「アイルランド共和国暫定政府からアイルランドの国民へ」――イースター蜂起時の独立宣言書
不肖わたくし、教育におけるナショナリズム研究をライフワークにしています。基本的には、ナショナリズムには利なし、人類社会はそこから抜け出さなければならないと考えています。ですので、「イングランドに長いあいだ支配されたアイルランドがかわいそう。イースター蜂起残念でしたね。自分たちの国家の建設をめざす動きはすばらしいものでした」などというスタンスは採りません。歴史的な経過の中で、ナショナリズムなるものがどのように作用したのかという話をしているつもりです。ナショナリスト(アイルランド国家の樹立をめざす人たち)だけでなく、数からいえば多数派ではないもののユニオニスト(連合王国の維持を望む人たち)もかなりいました。そして、地域差もありました。ロシア帝国やソ連政府が、ウクライナに(もちろん他の共和国にも)多くのロシア人を入植させ、ロシア語を国語にしていったために、民族や言語(や宗教)の構成はまだらになっています。前述したように、ウクライナのすべてが反ロシアではないし、特定の地域は熱烈に親ロシアだったりもします。ロシア語を話しロシアにシンパシーを感じる地域(クリミア)がウクライナから離脱することを、国際社会は、私たちは非難するべきなのか、容認すべきか、あるいは推移を見守るべきか。私にも正解なんてわかりませんが、アイルランド共和国と連合王国の人たちには非常に思い当たるふしがあるのではないでしょうか?
(当たり前のことですが、今回ロシア政府が事前・事後にとっているもろもろの行動を是とするつもりはまったくありません)
PART3へつづく
|