Mon deuxième voyage à l’Allemagne
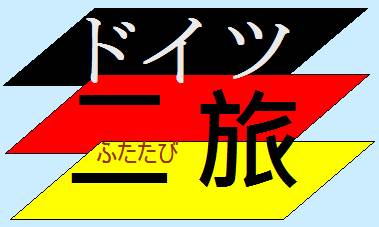 PART 8 ライン下り@ICE-DB ―車窓に釘づけの列車移動―
PART 8 ライン下り@ICE-DB ―車窓に釘づけの列車移動―
例のコンセントの問題がどういうことだったのか、ここで説明しておきましょうか。

 (左)ドイツのコンセント(フランクフルト、ホテル・ハンブルガー) (右)フランスのコンセント(パリ、レスペランス)
(左)ドイツのコンセント(フランクフルト、ホテル・ハンブルガー) (右)フランスのコンセント(パリ、レスペランス)

 左がフランクフルトで購入したアダプタ 右が東京から持参したもの
左がフランクフルトで購入したアダプタ 右が東京から持参したもの
写真を見ていただくとおわかりのように、プラグ側の金属導体の形状と長さは同じで、コンセント側が埋め込み型になっているのも同じですが、ドイツのほうは外穴の両側に微妙な凸凹がついています。持参したアダプタは白いはかまの部分がふくらみすぎていて、外穴につっかえて進まないのですね。もちろんこういう場合に小は大を兼ねるので、フランクフルトで買ったごっついアダプタを後日パリで試してみると、何の問題もなく使えました。ドイツ全体がそうなのか、国や地域ごとに小さな違いがあるのか、次回渡欧するまでに少し研究してみようと思います。

 ホテル・ハンブルガーの朝食
ホテル・ハンブルガーの朝食
2月24日はライン川沿いに下流方面をめざします。ボンを16時44分に出て、ケルン経由でパリに戻る切符を1月の段階でネット予約しており、19日にパリ北駅でチケットを発券してもらっています。フランクフルト〜ボンは180kmくらいですから、この日もかなりゆっくり使えます。じわじわボンに向かってもいいし、一挙に進んでもよい。ちょっと考えて、ボンに直行するほうを選びました。もう宿泊がありませんので、コインロッカーを使うにしても、荷物をもって降りたり乗ったりするのは面倒ですし、ボンでゆっくり見学するほうがよさそうだと思ったのです。となると、またしても「飛び道具」のICEを使うのがいい。朝食を済ませ、9時前にチェックアウトして、フランクフルトHbfに向かいました。

フランクフルトHbfの切符売り場 番号票を受け取って待つ銀行方式で、上のモニターで呼び出される
ここの切符売り場は大都市だけあって非常にスマートで、銀行のように番号票を受け取り、座って待っていればカウンターが空いた順に呼び出されるというシステムでした。パリは大都市だけど大行列が当たり前だもんなあ。いつものように、メモ帳に希望の切符を手書きして渡し、英語で発券を依頼します。9時42分発のICE1026便の指定券は問題なく確保できましたが、€43.50(うち指定料金€4.50)とまたも予想以上の値段。まあ日本でも新幹線に2時間乗ったらそれくらいするかなあ。これから乗る区間は高速規格の新線ではなく、いわゆる在来線ばかりなのだけど、こちらの運賃体系は新幹線と在来線を区別していないのかもしれない。長距離切符を購入して有効期間内に途中下車を繰り返すという手がなくはなく、それをしたらかなり安上がりではあろうと思いますが、特急料金の付加がどうなるのかよくわからないのと、何よりいつどのように行動するかそのときにならないとわからないのとで、今回は1回ごとに買いなおす方法を採りました。今回の遠征、事前に安いやつをネット予約したパリ→ストラスブールとボン→パリを含めて26,000円くらいです。ユーレイルのフランス&ジャーマンパス(4日間)は2等でも国内価格36,000円以上しますので、ちょいちょい買うほうが、それでもかなり安いですね。ただ学生だと、TGVなどの事前予約にしてもユーレイルにしてもかなり割引がありますので、また別の話。そして、もし現地に行かれるのでしたら国際学生証をお忘れなくね!


(左)風格のあるフランクフルトHbfの正面 (右)駅を背に見たカイザー通り

 フランクフルトHbf構内の軽食ゾーンで、コーヒー
フランクフルトHbf構内の軽食ゾーンで、コーヒー
あっさりと切符を買え、まだ30分くらいゆとりがあるので、構内の一角にある軽食ゾーンに足を運びました。お持ち帰りのサンドイッチ屋さん(西欧&中東)、ビールバー、例のシーフードカフェテリア、バーガーキング、寿司屋さんなどが並ぶ真ん中に円形のドリンクカウンターがあったので、スツールに腰掛けて「コーヒー」(€2.30)を一服。味うんぬんはともかく、ドイツの都市では、駅をうろうろしていればあまりお金をかけずに腹が満たされるような気がします。このゾーンに隣接して売店があったから、エヴィアンのペットなどを買って小銭をつくりました。発車8分前くらいにホームへ出てみてもそれらしい列車の影はまだない。ここが始発でないので不思議ではないけれど、そのあたりにいた卒業旅行らしい日本人の男子学生3人連れに「ICEはこのホームですよね?」と確認して、指定された6号車のあたりに向かいました。前述したように、ドイツの幹線鉄道は主として南北方向に走っていて、この地方(バーデン・ヴュルテンベルク州〜ラインラント・ファルツ州)ではライン川にほぼ並行しています。ところがフランクフルト・アム・マインはライン川に流れ込む支流のマイン川に面していますから、この都市に立ち寄ろうとすると、縦のラインからいったん東に張り出してフランクフルトに突っ込み、折り返すように元のラインに復帰することになります。フランクフルトHbfは行き止まりのターミナルであることもあり、いまから乗るICEもスイッチバック(方向転換)を余儀なくされるのです。クロスシートを進行方向に向ける日本の鉄道では、スイッチバックがあると「みなさま、座席の方向転換にご協力ください」なんて呼びかけがあり、名古屋〜岐阜〜高山を結ぶ「ワイドビューひだ」などはその配慮を惜しんでか岐阜まで逆向きに進む。こちらの列車は、そもそも進行方向に座ってもらうという配慮がいっさいなく、クロスシートが回転することもないので、スイッチバックがあっても影響はないでしょうね。私に割り当てられた座席はやっぱり後ろ向きでした・・・。


さらばフランクフルト
9時42分の定刻からほんの少し遅れて発車。きのう見てびっくりした大都会のビル群を見やり、マイン川を鉄橋で渡り越して郊外に出ましたが、すぐフランクフルト国際空港(Flughafen Frankfurt am Main)駅に着きました。これほど都心に近く、しかも新幹線が直接乗り入れるハブ空港なら見事なもので、成田空港の切なさをまた思う。空港駅を出ると、農村地帯に大規模な工場の煙突がぽつぽつという不思議な景色に出会います。オペルの工場も見えました。やがてライン川をほぼ垂直に渡って左岸に移り、ほどなく10時18分にマインツ(Maintz)Hbfに到着。駅前に見える建物の色づかいは渋い赤褐色で、フランクフルトの新市街から来たためか「これぞ欧州」という感じもします。新しいのが好きなのか嫌いなのか、私はっきりしませんね。
DBご自慢の高速列車ICEとはいえ、カーブだらけの在来線ではなかなか速度を上げられません。10時33分ころ、列車はライン川の左岸に取りつき、そのまま堤防に寄り添うように、ときに堤防の上を走るようになりました。ストラスブールあたりで見るよりも川幅が広くて、両岸に河岸段丘が迫っているので、凹型のくぼみの中を水が流れている感じがします。先ほどのマインツが、いわゆるライン下りの上流側の起点。興味がなくはないけど、1人で船に乗って何時間も川下りするのもねえ。鉄道なら何時間でも平気なので、好き好きかね。


(左)ライン川に寄り添って走る(写真左が下流方向) (右)観光船
地理の教科書的には、「ライン川は代表的な国際河川で、内陸水運の動脈としても使われています」ということになります。たしかに観光船だけでなく、さまざまなサイズ、種類の貨物船が上り下りしていました。船籍を示す国旗に注目していたのですが、オランダとベルギーが目立ちました。これはたまたまかもしれません。対岸にも道路と鉄道が見えて、だいたい同じような間隔で左右両岸に小さな町が現れます。大きな都市がないせいか、両岸を結ぶ橋はまったくありません。記憶ちがいかなと思ってあとで地図を追ってみましたが、たしかにないのです。ライン川はときどき大きく曲がり、そのたびに線路もお付き合いして、どこまでも左岸から離れません。ライン川沿いに進むのだし、車窓からそこそこ見えるのかなと思っていましたけれども、これほど長時間にわたってライン川を見られるとは思いませんでした。鉄道旅行で、車窓から目を離せないほどになったのは本当に久しぶり。あまり夢中になりすぎて、肩をとんとんと叩かれるまで、女性車掌が検札に来たのに気づかなかったくらいです。



10時45分ころ、ライン川ともども右に大きく曲がったと思ったら、今度は左へと、急カーブが連続する箇所にさしかかりました。50分ころ、小さな河港らしい、かわいい町が現れて、ザンクト・ゴアー(Sankt Goar)の駅名票が見えました。川の景観もすばらしいし建物もキュートだから日本人観光客なら好きそうだなと思っていたら、帰国後に地図で確認したところ、かのローレライ(Loreley)のそばだったらしい。いつものように予習していませんし、ライン下りとかローレライとかいうのはミーハーな観光の世界だと思い込んで、関心をもっていなかったのです。何ともお恥ずかしい。でも、予期しなかったからこそ、いい眺望を得られてよかったとも思います。
 両岸に小さな町 対岸にはお城も見える
両岸に小さな町 対岸にはお城も見える
 対岸の段丘上に見えたお城(調べたら「ねずみ城」だそうです)
対岸の段丘上に見えたお城(調べたら「ねずみ城」だそうです)
 対岸に見えた町(詳細不明)
対岸に見えた町(詳細不明)
かなりの規模の街が見え、11時10分にコブレンツ(Koblenz)Hbf着。マインツを出発したライン下りの観光船は、ここが終点になります。フランクフルトに迷い込まなければ、ここで降りて泊まるのも有力な候補だったのです。何となく、そのうちまた来そうな気がします。ホームには、この列車を下りたらしい日本人の男性2人連れが見えました。
コブレンツは、ライン川にモーゼル川(Die Mosel / la Moselle)が合流する地点に発達した都市で、古くから交通の要衝として大きな役割を果たしました。モーゼル川といえば白ワインの生産地として有名で、3年前にメス(ロレーヌ)→ルクセンブルクと旅した折には、この川の中流に沿って北上したのでした。はるばる流れて、ここまで来るのね。列車がコブレンツHbfを出てすぐ、車窓右手に合流地点が望めました。ドイチェス・エック(Deutsches Eck=ドイツの角)と称する名所だそうです。今度ぜひ行ってみたい。


モーゼル川がライン川に合流する地点(Deutsches
Eck) 中洲があるため2本の川のように見える
ここからは、ライン川が見えたり見えなくなったりを繰り返します。11時20分ころ、両岸の河岸段丘が低くなり、かなり大きな斜張橋が見えました。帰ってから調べたところによればヴァイセンツルム(Weißenthurm)という町らしい。ライン川が峡谷のような「川下り」エリアを抜け出して、いよいよ下流の平野部にさしかかったようです。
 ライン川との並走区間も、そろそろ終わり
ライン川との並走区間も、そろそろ終わり
11時42分、ボン(Bonn)Hbfに到着しました。フランクフルトからジャスト2時間、そのうち1時間ほどもライン川と並走してきたわけで、これまであちこちで乗ってきた鉄道路線でもきわめて高得点の区間だったと思います。指定席がたまたま川岸の側だったのも幸いしました。遠征最終日の午前中に、何とも有意義な時間を過ごせました。フランクフルトHbfで出会った3人連れの学生は同じ車両に乗っていたようで、下車する際に目が合ったから、ボン・ボワイヤージュ(Bon voyage よい旅を)と声をかけておいた。

 ボンHbf
ボンHbf
この街での持ち時間は5時間ほど。地図で確認して、さほど大きな都市ではないことがわかっているので、それだけあれば十分に回れることでしょう。この中央駅はホーム2面3線と小さく、コンコースもきわめてかわいくて、せいぜい私鉄の急行停車駅くらいの規模。ただ、駅の東西を結ぶ地下通路が広くて、そこにかなりの数のコインロッカーがありました。雨が降りそうな様子はないので折り傘も取り出さず、例のごとく手ぶらですっきりしました。重たいガイドブックは、またまたロッカーの中。ツーリストインフォメーションに立ち寄って観光マップを入手してから街歩きを開始したいと思います。
この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。