Mon deuxième voyage à l’Allemagne
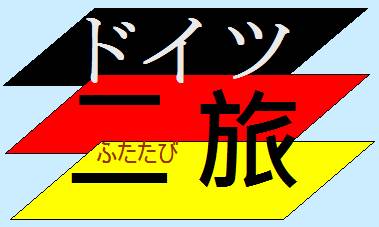 PART 7 フランクフルト ―迷い込んだ大都会で困惑―
PART 7 フランクフルト ―迷い込んだ大都会で困惑―
23日の朝は7時半ころ起き出して、レセプションと同じ階にある朝食ルームで朝ごはん。基本はパンとホット&コールドの飲み物、シリアルで、チーズと何種類かのハム・ソーセージも用意されていました。写真のような丸くて硬めのパンはドイツではよく見るものらしい。ナイフで横に切ってハムをはさむのです。


8時半ころチェックアウトして、今日も絶え間なくやってくるトラムに乗り、中央駅に向かいました。時刻表によれば、9時10分発のIC(インターシティ)がフランクフルト10時40分着、10時ちょうど発のICEなら11時08分着で、それほど所要時間に差がありません。以前であれば、鉄道旅行の本筋はこちらとばかりにICを選んでいたと思いますが、趣向が変わったのか羽振りが多少よくなったのか金遣いが荒くなったのか、ほとんど迷わずICEの切符を頼んだのだから、われながらちょろくなったものです。カールスルーエHbfの切符売り場で、メモ帳に必要事項を書いて手渡し、英語でフランクフルトまでのチケットを頼みます。席を指定したほうがいいですかねと訊いてみたら、女性職員がそうですねえ・・・と首をひねり、コンピュータでぱちぱちやって、「残念ながらトゥーレイト(遅すぎた)。指定はとれません」と。込んでいるにはちがいないですが、どこかには座れるんじゃないでしょうか。昨夜ソーセージ定食?をいただいた駅の食堂のドリンクコーナーからエスプレッソ(€1.90)をとり、しばらく休憩します。この日も朝からずっと雨で、5日前に西欧へ来てから、まったく降らないという日に当たりません。
ICE278列車は、前日オッフェンブルクから乗った276の1本前(2時間前)の便で、やはりベルリン行き。けっこう込んでいましたが、窓際の空き席を見つけて座れました。今回も所要1時間と小刻みな移動になります。それにしては、チケットが€37とかなり高めになりました(前日のストラスブール→オッフェンブルク→カールスルーエは€19)。日本のように運賃+特急料金というのではなく包括運賃制なのと、航空運賃のように「相場」がいろいろあるのとで、このあたりがよくわかりませんね。

 フランクフルトHbf
フランクフルトHbf
278列車は途中マンハイムHbfに停車し、この日も定時運行でフランクフルト・アム・マインHbfに着きました。都市名としてはフランクフルト・アム・マイン(Frankfurt am Main)と、この街を流れる川の名を冠して呼びます。ICEがHbfに到着するすこし前に、そのマイン川を鉄橋で渡ると、車窓にはこれまでの森林とか田園とは何もかも違う別世界、絵に描いたような大都会が現れました。高層ビルが林立しているのが一目でわかるほどで、西欧のというより(行ったことはないけど)アメリカの都市みたいな見た目の印象があるなあ。そもそも当初は、先ほど通ってきたマンハイムとかマインツ、あるいはもう少し先のコブレンツあたりで泊まろうかな、などと思っていて、アダプタの件が出てくるまでフランクフルトは眼中にありませんでした。いつもいうように、私は大都会育ちで田舎が苦手なほうですから、大都会に怖気づくということではありません。ドイツを訪れようと考えるときに、フランクフルトの優先順位が高くないというだけのこと。これはもしかすると一般の旅行者もそうかもしれない。フランクフルトには西欧でも屈指のハブ空港があり、ここで飛行機を乗り継いだという話はよく聞きますし、何しろ経済の中心だからビジネス関係の人は多く訪れるのでしょうが、旅行となるとねえ。この街のシンボルって何だったっけとか、どんな見どころがあるのかなど、いつも以上に予備知識がない(笑)。「ドイツ」のガイドブックをぱらぱら読んでみたけど、行くはずのないベルリンとかミュンヘンのところをおもしろがっていて、フランクフルトは飛ばしたくらいだから!
ともかくもやってきたフランクフルト。これはご縁、ないし神様のお導きですから、存分に街歩きしませんとね。まずはホテル探し。荷物をコインロッカーに入れ、都心をうろうろしてアダプタを購入できれば、また列車に乗ってどこかへ行けるのですけれど、そうなると「次の都市」に夕方以降の到着になって動きがとれなくなります。この中央駅は、線路数は多くアーチ型の天井も高くて立派ですが、エントランスとホームのあいだの距離が短くて、付帯施設のゾーンは広くないみたいです。エントランスに近いところにツーリストインフォメーションがあり、すでに10人くらいの人が2列に並んで番を待っていました。順番が来て、いかにもゲルマン系という顔立ちの50歳くらいの女性職員に、駅近くのシングルルームの手配を頼みました。せっかく大都会に来たことだし、少しグレードの高い部屋にしてもいいかなと考えて、€80〜90あたりで探して、というと、「エイティー?? そりゃまた張り込みますねえ。それだけ出せばかなりナイス・ステイになりますよ」と。当方の風体を見て€60くらいの客だと思ったのか(そうなんだけど)、インフォメを当日訪ねて宿を取ろうという人はだいたいそうなのか(そうなんだけど)、意外そうな感じです。いくつか調べてくれて、「この駅のすぐそばに、€75のところがありますがいかがですか? とてもよいビジネスホテルで、必ずよい夜を過ごせますよ。私は勧めます」と、明らかにドイツ語なまりの、しかし明瞭な英語でいいました。それなら異存なく、手続きを進めてもらいました。この手数料が€3.00。€0.50と出ている観光マップを買おうとしたら、「これはさしあげます」と微笑んで、日本語・中国語の一体となったバージョンを手渡してくれた。ただこれ、地図の構成や表記に問題が大ありで、あまり役立ちませんでした。夜になってからホテルに置いてあったタダのいいやつに気づいたので、なおさら残念に思います。自分から買い求めるなら日本語版は選ばなかったはずですし。


今夜のホテル 玄関のドアを出ると、そこがフランクフルトHbf
いま手配したばかりのホテル・ハンブルガー・ホーフ(Hotel Humburger Hof 「ハンブルク館」てな感じかな)は、駅舎の横に面した数軒のホテルの1つでしたので、徒歩2分もかかったかどうか。11時半にもなっていないからチェックインできるか微妙なところです。ああ、これは「ビジネスホテル」だ。日本の地方都市に出張したりするとき泊まるのはほぼこのタイプ。自動ドアを入ると清潔なフロントまわりがあり、きちんとスーツを着た男性が迎えてくれました。€50くらいの安宿だと、個人経営で、どちらかというと旅籠(はたご)みたいなウェットな感じもするものね。すぐにチェックインさせてくれ、案内もきわめてスマートでした。エレベータや廊下はマンションみたいな感じ。博多駅周辺のビジネスホテルは、いつかマンションに造り変えることを前提に設計しているといった話を聞いたことがありますが、そういうことなのかしら? 部屋に入って最初にすることは、そう、コンセントの確認! ここもカールスルーエと同タイプで、やはり当方に問題ありでした。
 清潔な「ビジネスホテル」
清潔な「ビジネスホテル」
もらったばかりの地図を開き、ガイドブックの該当ページを一通り読んで、街の構造みたいなものを頭に入れます。何しろ「大物」なので、地理の把握には中小都市とは違う頭の使い方をしなくてはなりません。中小都市では、駅・目抜き(中心市街地)・イチ押しスポットの3点を押さえて、三角形のかたち(ゆがみ方)を頭に入れ、ライン川といった「川」があれば三角形をそれに載せるというやり方をします。大都市の場合は、地区ごとに分解して、もう少し複雑な手法をとります。これは国内でも海外でも変わらないやりかたで、もう20年もしております。
中央駅に戻って、地下鉄で中心市街地のハウプトヴァッヘ(Hauptwache)あたりをめざそう。フランス語圏では地下鉄をメトロ(métro)と呼び、なぜか東京地下鉄もその呼称を採用していますが、ドイツではウーバーン(U-Bahn)。ただ、フランクフルトの場合は、DBの近郊鉄道であるエスバーン(S-Bahn)も都心部で地下を走っているため、同じような感覚で使えるそうです。総武快速線と横須賀線が錦糸町〜東京〜品川間で都心の地下を走り抜けていますが、あれがもっと多方向に展開していると思えばいいでしょうか。フランクフルトは運営主体にかかわらずゾーン制運賃を採用しているため(この点はパリも同じ)、UバーンでもSバーンでも「地下鉄」には違いないのです。フランクフルトHbfの地下1階に下りると、そこにはいくつもの路線が乗り入れていて、どれか適当なやつに乗って都心に出られそうです。ところが、ここの地下鉄には改札がなく、歩いていくとそのままホームに出てしまいます。地下1階に自動券売機があって、そこで切符を購入すればいいわけですが・・・表示がことごとくドイツ語! いや、たしかに英語もセレクトできるようになっているが、どうすれば英語になるかという肝心の部分がドイツ語で書いてあり、きわめて不親切。券売機には駅名がずらずら並べてあって、それを押せば望みのところまで発券されるのかもしれませんけど、あるはずの一日乗車券がどれなんだかさっぱり不明なのです。有人窓口でもあればいいのに、それが見当たりません。何人かにヘルプを求めても、みな嫌がって教えてくれないし、ようやく立ち止まってくれた清掃員らしい男性は、質問の趣旨はわかったようだけど英語を一言も解しないらしく、いっていることのすべてが意味不明。うわー。地下鉄で切符を購入するのにこれほど難渋したのは生まれて初めてで、鉄道通も言語の壁は崩せなかったか(涙)。
やむなく、ホテルの部屋をとってもらったインフォメに戻って、さっきとは違うおねえさんに「地下鉄の一日乗車券を買いたいのだが要領がわからなくて・・・」といいかけたら、「それならここで買ってください」と、すぐに出してくれました。たしか€5ちょっとだったと思うのに、出してくれたのは観光客向けにさまざまな割引特典のついたFRANKFURT CARDという€8.90のやつだった。ここのカウンターで訊ねれば当然こういうのを出すんでしょうね。いまさら「券売機の使い方を教えてくれ」ともいいにくいし、授業料ぶんと考えて、これを引き取りました。どうも調子がよろしくない。


そんなことをしているうちに腹が減ってきました。駅のホーム周辺には軽食店がいくつも出ていて、その中には簡易テーブルを出して食事できるようになっている店もあったから、駅ランチして態勢を立て直すということにしようか。のぞいたお店は、数種類の肉とか魚に、野菜やポテトを付け合わせるカフェテリア方式で、注文を受けてから主菜を調理するようで、ビール(例のBECK’S)を飲みながらできあがりを待ちます。頼んだのは、白身魚のフライにフライドポテト、まあ要するに英国でいうフィッシュ&チップスですね。ビールも込みで€9.20。フランスといいドイツといい(もちろん英国もベルギーも)、フライドポテトばっかりよく食うねえ。フランス人がドイツの悪口をいう際に、「コロンブスがじゃがいもを運んでこなかったらドイツは発展しなかった」なんていうのですが、お前さんたちだって同じじゃないの?

チケットを手に合法的に?乗り込んだ地下鉄は、UバーンのU4系統。ハウプトヴァッヘには行かないようだから、その東側のコンスターブラーヴァッヘ(Konstablerwache)で降りてみました。構内が広々として、多くの人であふれています。地上に上がると、商業地のメインストリートらしきにぎわい。目抜きのツァイル通り(Zeil)なのですが、駅のすぐ前に、あった! 大型電器店だ!
 お世話になりました
お世話になりました
何となく、電子機器とかそのあたりに関しては、フランスよりドイツのほうがしっかりしていて信頼できそうです(なんていうのがネイション偏見です)。店を入ってすぐ、レジのそばに、各種のアダプタを並べていたので、間違えたらいけないとわざわざ持参した使えないアダプタとつき合わせて、慎重に調べてみます。ところがどうも違う。ちょうどそのとき、若い男性店員が箱をもってアダプタ関係を補充に来たので、「この商品について教えていただけませんか」と英語で訊いてみました。手持ちのアダプタを見せると、「いや、これはドイツで使えるはずですよ」と。「試してみたのですが、この部分が外穴につっかえて入らないのです」と、はかまをなでながら説明し、わかってもらいました。事情を呑み込んだ店員さんは、奥のほうの別のスペースに連れて行き、あるアダプタを示して、これだという。「アメリカン・タイプの機器をジャーマン・タイプのコンセントにつなぐなら、このアダプタです」。アメリカと日本が同一だったか自信がなかったので、充電器のジャパニーズ・タイプを見せ、これはOKですかと問えば、もちろんですと。超ダンケシェーン。€4.99と、かなり立派な値段でしたけどね。まあ先進国を旅しているのだから、どこかで手に入るのはわかっているのですが、どきどきしたねえ。いま写真のファイルを見ながらこの原稿を書いていますが、2月23日のフォルダは露骨に写真数が少ないもんねえ・・・

 ツァイル通り
ツァイル通り
お店を出てツァイル通りを西に歩きました。両側にショーウィンドウの並ぶ商業地区のようです。ほどなく、デパートやショッピングセンターも建つゾーンに出ました。午後になっても雨がやまず、空が暗いこともあって、人出はけっこうあるのだけど気勢が上がりません。H&Mなどのカジュアルブランドが見えたので、まあ渋谷か新宿か、都心の商業地であることは間違いないようです。どうもまだ、「予定外でここに来ちゃった」という思いを拭いきれないのか? 大型のショッピングセンターに入ってみて、普段なら大いに気分をよくするところなのに盛り上がらないあたり、やっぱり来るところと時期を間違えたかもしれない。
 吹き抜け式のショッピングセンター
吹き抜け式のショッピングセンター
歴史散歩をして気分を変えようと、地下鉄を乗り継いでドーム/レーマー(Dom / Römer)駅へ。1回乗り換えがあるので、歩いたほうが早いくらいなのですが、高めのチケットを買っているので少しくらい乗らないとね。下車したあたりの地区は、歴史的な意味ではフランクフルトの中心のようです。
 大聖堂
大聖堂


赤褐色の概観が印象的な大聖堂(Frankfurter Dom)がありました。さっき歩いたあたりは新宿と変わらぬ雰囲気だったのに対し、この周辺は一転してクラシックな建物が並び、旧市街といえそうです。大聖堂に入ってみると、思ったほど大きくなくて、でも採光がよく明るい。造りはカトリックのそれに間違いないけれど、プロテスタントの教会のような明るさもあります。外観も内部もレンガ色なんですね。この大聖堂は、16世紀以降の神聖ローマ皇帝の戴冠式がおこなわれた場所です。16世紀といえばフランス語でシャルル・カン(Charles Quint)と呼ばれるカール5世(Karl V)が非常に有名。世界史の不得意な人は、ドイツのカール5世がスペインに行くとカルロス1世(Carlos I)になるんだよというあたりでキレそうになるかもしれませんね。彼は1519年にハプスブルク嫡系の領地を世襲し、選帝侯(Kurfürst)により神聖ローマ皇帝に選出され、ここで戴冠しました。ルターの反逆に困惑し、オスマン帝国の進撃を食い止め、世界の海に乗り出したスペインをどうにかまとめ、フランスとイタリア戦争を戦った超多忙な君主でした。前述のように、ドイツは19世紀後半にいたるまで諸侯が分立して国家的統一を果たせませんでした。三十年戦争(1618-48年)のあとは神聖ローマ皇帝の神通力すら失われていき、皇帝は要するにハプスブルク家の支配地であるオーストリアの君主でしかなくなっていきます。ただ、皇帝という称号をもつのは(ロシアを別にすれば)欧州でただ1人、神聖ローマ皇帝ですから、手続きとか儀式は厳格に守られたようです。フランクフルトはそうした儀式の場になっていきました。大聖堂の中にミュージアムも併設されていたので、そのへんを勉強していこうかと思ったら、「もうクローズしました」だって。
 レーマー
レーマー
大聖堂のすぐ近くに、地区の名にもなっているレーマー(Rëmer)があります。これも16世紀に遡るものらしく、以前は市庁舎であったらしい。このレーマーの前の広場には、同じような独特の三角屋根と木組みの窓枠をもった建物が並んでいて、歴史地区らしい景観を見せています。ロンドンでもパリでも、もともとの市の中心は川のすぐそばにあります。「マイン川沿いの」とわざわざ地名に冠するフランクフルトも例外ではありますまい。
初期近代のフランクフルトは宗教・政治都市から経済都市へと徐々に変貌していきます。神聖ローマ帝国に属する諸邦の多くは公・侯・伯などの殿様が治める領邦(Territorium)でしたが、一都市でありながらこれと対等な立場にある自由都市の1つでした。皇帝の選挙や戴冠式がおこなわれるくらいですからその地位の高さがうかがわれます。今回、西欧にやってくる少し前に、例の谷川稔さんの「フランスとドイツ―国民国家へのはるかな道」(『世界の歴史』22巻、中央公論新社)を読みなおしてみました。仏独いずれも本当に「はるかな道」だったことはストラスブールの回で述べたとおりです。ドイツでは、覇権をめざすプロイセン、伝統的な支配権を固守しようとするオーストリア、産業革命を背景に市場の統合をめざしたいブルジョワ勢力、自由主義者、ナショナリスト、いろいろな利害が絡み合って事態は容易に進みませんでした。1848年、フランス二月革命は欧州各地に飛び火し、ウィーンでも革命が起きてメッテルニヒ長期政権が倒れ、当人たちは正統主義、論者は反動と表現するウィーン体制が崩壊します。この流れの中で、ドイツ統一を一挙に果たそうと、フランクフルト国民議会が召集され、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世を皇帝として戴く方針が採択されますが、王が辞退したことなどもあって挫折しました。近代国家に不可欠の強力な中央政府、それを支える軍事力と財政基盤、そして官僚制が整っていなかったのですから、仮にOKしていても国家統一にはいたらなかったことでしょう。フランクフルトは、地理的にも、経済的にも、前述したような自由都市としての性格からしても、ドイツ全土の領邦が代表を送り込むのにふさわしい都市ではあったように思います。いまはロンドンと並ぶ西欧経済の中心都市で、経済ニュースで世界の株価情報が紹介される際に日経平均(東京)、ダウ(ニューヨーク)、FT(ロンドン)、ハンセン指数(香港)などとともに出てくるDAX(Deutscher Aktienindex ドイツ株価指数)はフランクフルト証券取引所における指標。また、ユーロ圏の金融政策を担う欧州中央銀行(European Central Bank: ECB)もフランクフルトに本拠があります。ユーロ発足に際して、分権的なドイツにおいて連邦政府や州政府から自立した中央銀行であるドイツ連邦銀行(独連銀)をモデルにしてECBがつくられたためといえそうです。いうまでもなくここ数日ユーロにはさんざん世話になっていますので、間接的にはフランクフルトのご助力をいただいていることになるかもしれません。
 雨に煙るマイン川
雨に煙るマイン川
レーマー広場をうろうろしたあと、すぐその南側を流れるマイン川の左岸に出てみました。うん、これは都市景観にマッチした川ですね(隅田川みたいな意味で)。雨がやまないのが返す返すも無念ではあります。レーマーの北側、先ほど歩いた繁華街のツァイル通りにつながるあたりはやっぱり商業地で、小規模な小売店や飲食店が軒を連ねていて、若い人を含めてかなりの人出があります。平日の15時にもなっていないのに、どうなっているのかな。少し歩いたところに、Liebfrauenbergという小さな広場があり、そこに面して同名の上品なカフェがありました。もうドイツ語の読みを考えるのもかったるくなるほど気分的に疲労しました(いまこれを書きながらGoogleの地図を参照しているのですが、このカフェの店名が地図上に示されていてびっくり)。ビールは、地元の産らしいBinding Römerのピルスナーで、0.3リットルで€2.40とかなり安い。0.4リットルだと€3.00だそうです。シルエットの美しい細長いタンブラーに入って出てきたビールは、淡い黄金色というのでしょうか、見た目が美味そう。軽い飲み口だなと思ったら、けっこうしっかりしたタイプではありました。ドイツにはビール法という法律があって、ビールに麦芽とホップと酵母以外の原料を用いることが厳禁されています。法とは何ぞやという件でよく話題に上るので、法学部の人などはご存じかもしれません。1516年にバイエルン公が勅令として出し、1871年のドイツ統一に加わる(同格のはずのプロイセンの軍門に下る)条件としてこの法を帝国全土に布告することを求め、受け入れられたものです。日本のビールは、ヱビスやプレミアムモルツなどを例外として、だいたいにおいて米やコーンスターチなどの混ぜ物を含んでいるので、ドイツにもってくればビールと認められません。まして発泡酒だとか第三のビールなんて!

私は、課税基準をクリアするために本来の原料を削ってニセモノで代用し、あたかもビールのような味に仕立てるといったビール会社の所業はとうていイノヴェーション(技術革新)と認めたくないし、何より味がマズイので、発泡酒や第三のビールは口にしません。日本のビールは味のバリエーションに乏しいけれど、それでも品ごとにちゃんと味がある。ビールとニセモノなんてまったく違うと思う。消費者(酒飲み)の多くは、そんなのどうでもいいのかね。私が日々愛飲しているサッポロ黒ラベルにも、米とコーンが入っています。インチキではあります。欧州に来るといろいろな種類のビールを飲んで、「やっぱり本場のは美味いねえ」なんて思うのだけれど、帰りのANAに乗って、お飲み物は何にいたしますかと訊かれるとまず「サッポロ!」っていうんだよね。このへんアマチュアですかね。

 フランクフルトのUバーン
フランクフルトのUバーン
足と気分の両方が疲れてきたので、いったんホテルに戻ることにしました。パリにいるときも、ホテルの部屋とかカフェでじっとしたり、本を読んだりする時間がけっこう長いのです。初心者とか旅慣れていない人は、せっかく来たのにもったいないというので、むやみに歩き回ろうとするのですが、日ごろの行動を考えればそんなの無理ですって。21日の早朝にパリを出てから今日で3日目で、ほとんど歩きつづけているように思いますので、そろそろ休んだほうがよろしかろう。フランクフルト泊まりにしてよかったと思います。これで次の都市にいってまたうろうろするのでは、翌日に響きます。Uバーンに乗ってフランクフルトHbfに戻ります。中央駅と中心市街地の関係は、名古屋における名古屋駅(地元では名駅=めいえき と呼ぶ)と栄(さかえ)の感じによく似ています。距離的にもそのくらいではないかな。駅のほうはホテルと銀行ばっかりというのも似ているね(河合塾はないけど)。部屋に戻ると15時半。あとで夕食がてら、また歩くとして、17時までベッドで昼寝。んでその間に、待望の充電を。
 フランクフルトHbfで顔を合わせた独仏のスター列車 DBのICEとSNCFのTGV
フランクフルトHbfで顔を合わせた独仏のスター列車 DBのICEとSNCFのTGV
17時半ころ表に出ると、まだ日没前でした。昼間歩いたツァイル通りにつらなる東西の道が商業的なメインストリートのようだから、もう一度そのあたりに行ってみよう。ところが寝ぼけていたのか大都会式の歩き方に戻れていないためか、Sバーンの上下を間違えてしまい、電車はトンネルを抜けて市内西側の高架線に出てしまいました。メッセ(Messe)駅で引き返します。そろそろ通勤客が自宅へ戻る時間帯にさしかかっているようで、けっこう混雑していました。郊外線にも乗りたいようなことを申しましたが、この付近はまだ都心のつづきで、ビルが建ち込んでいます。同じ線路を都心方向に戻る電車に乗ると、車両の端に立っていた2人組、背が低くてぼろぼろのジーンズをはいて、白人ではないふたりが、突然歩き出して乗客に切符の提示を求めました。覆面チェックなのかそういうものなのか、噂に聞いた車内検札のようです。ドアのそばに立っていた若い男が無札で引っかかり、罰金を取られました。私のところへもやってきたけど、もちろんセーフ。検札員はにこりともしないで次の車両に移りました。パリでもどこでも、検札員が抜き打ちでやってきて、無札だと何十ユーロもの罰金を取られるぞと聞かされていましたが、実際に見たのは初めてです。パリのメトロは(均一運賃のため入場時だけ)改札機を通るものの、ここフランクフルトは信用システムですから、こういう作業を頻繁にしているのかもしれない。トータルで見てどちらのほうが合理的なのか、よくわからない感じはします。
 ハウプトヴァッヘ
ハウプトヴァッヘ
昼間も使ったハウプトヴァッヘは、SバーンおよびUバーンの路線が集中する大きな地下駅で、構内には常設のカフェやファストフードだけでなくパン屋や野菜屋の屋台が出るなどにぎやか。駅と市街地の関係が名古屋の名駅と栄に似ていると申しましたが、地下の造りや人の流れはたしかに栄のような感じですよ。あんなにバカでかい地下街はないけどね。さっき来たのとは逆の西に向かって歩いてみます。グローゼ・ボッケンハイマー通り(Große Bockenheimer Straße)で、日本流にいえば弁当横丁らしく、カフェテリアなどの軽食店や持ち帰り惣菜のお店がたくさんありました。ビジネス街に近接しているので、勤め人たちがランチや夕食用に買っていくのかもしれない。ちゃんとしたレストランもありました。天気がよければもう少しゆっくり散歩するところでしょうね。そのあと、折り返すようなかたちでゲーテ通り(Goethestraße)へ。ここは完全に高級ブランド街。広くない道路の両側に上品なショーウィンドウが並んでいます。たそがれていることもあって、品のよさがさらに増したようではありました。いつもいうように、ブランドにもショッピングにもまったく興味はないのですが、品物をディスプレイされたショーウィンドウを見て歩くのは好きなほうです。



グローゼ・ボッケンハイマー通り
 ゲーテ通り
ゲーテ通り
ゲーテ通りを抜けるとゲーテ広場(Goetheplatz)で、さすが世界の文豪、ゲーテ尽くしの界隈ですね。ゲーテついでに、彼の生家であるゲーテハウス(Goethehaus)にも行ってみましょう。もうクローズしている時間だろうし、ゲーテ自身にさほどの執着はないので、外観だけ見て「行ってきたよ〜」という報告ができればいいや。観光地としては目玉のようで、ゲーテ広場からハウスまでは、路上に示された標識をたどって迷わず行くことができました。


(左)ゲーテ広場のゲーテ像 (右)ゲーテハウス
さてどこかで夕食といこうかね。ガイドブックは重たいのでホテルに置いてきましたが、マイン川の対岸にあるザクセンハウゼン(Sachsenhausen)地区に行けば気楽なレストランがたくさんあると書いてあったから、足を伸ばしてみようか。トラムとSバーンを乗り継いでフランクフルト南駅(Frankfurt Südbahnhof)へ。ところがこのSバーン車内でハプニング! 空いているシートに座ったら、通路の反対にいた兄さんが「ぎゃー」みたいな声を上げる。あまり明るくない車内ながらよく見ると、私の座ったシートには粘り気のある黒っぽい液体が撒かれていて、どうもその上に腰を下ろしてしまったらしい! 兄さんが同情するような顔で見たので、サンキューといってから、人のほとんどいない隣の車両に移って、状況を確認しました。西欧にはぶっかけスリのような連中がしばしば現れますから、その場であわてて騒ぐのがいちばんよろしくないのです。黒いハーフコートのいちばん下についていたのは、トマトケチャップのようです。しょうもない連中がいたずらしたものらしい。コートのほうはほんの少しだったので濡らして叩けば大丈夫でしょうが、問題はスラックス。私はジーンズをいっさい着用しない人間で、仕事のないときはいわゆる綿パンで通しています。このときは、よりによって白い綿パン、そのお尻のところに真っ赤なケチャップが5cmほどにわたって無残にも付着していました・・・。まるで何かをやっちゃったみたいに見えるぞ。替えズボンなんてもってきていないし、いまからどこぞで新しいのを買うにしても、まずはこれをどうにかしないと。フランクフルトに着いたときからこの街に違和感があったのだけれど、こうなるのね!
夕食などと悠長なことはいっていられず、プレメトロ(トラムの車両が地下を走る)仕様のUバーンに乗って中央駅に引き返し、ホテルの部屋へ直行。パリ滞在中は1回か2回は下着などを手洗いするので、洗濯石鹸(て知ってる?)をもっていくのだけど、遠征には不要と思ってパリに置いてきてしまいました。洗面所兼シャワールームに置かれていたヘア&ボディ兼用のシャンプーを泡立てて患部?に塗り込み、水で濡らしてこすります。ごしごし。綿パン全体を洗っていると外出不能になるから、その周辺だけを洗うというきわどい仕方で、やってみたら汚れは完全に落ちました。対処が早くてよかったようです。幸い洗面所にはドライヤーもあります。短髪ですからそんなものもっていないし、理髪店以外で使ったことすらないのだけど、こういうときは便利ですね。しばらく当てていたら、すぐに乾きました。やれやれ。


19時半を過ぎていました。一日乗車券も元を取るほど使っていないし、夜はまだまだこれからですが、この街との相性が今日のところはよくないことを顧慮して、3たび市街地に出ることはやめました。24時間くらい前に急に思いついてここに来たのだし、もともと縁がなかったのかもしれない。とはいえ、人間や地域との相性を第一印象で決めつけるべきではありません。第一印象をやたらに引きずっていつまでも同じ評価を語りつづける人がいますが、そういう人は教育者に向かないと思う。19年前、友人とパリに初めて降り立ったとき、それまで南仏ののんびりしたところばかり歩いてきたせいか、都会のよそよそしさと落ち着かなさに参ってしまい、フランスの中でパリだけは嫌だなという印象をもったまま帰国しました。その感じを引きずったため、ほかならぬフランスを研究対象にするようになったのに、次にパリを訪れるまで8年を要しました。そのパリを、いまでは「地元」くらいに思っています。フランクフルトは世界経済の中心の1つですし、いずれまた来ることがあると思います。そのときにはきっと楽しいことがあるでしょう。
栄地区が栄えていたとしても、名古屋駅周辺だって捨てたものではないわけで、フランクフルトHbf近く、要はホテルの徒歩圏内でレストランを探しました。駅前から都心方向に伸びるカイザー通り(Kaiserstraße)を歩けば、タテ方向は普通の店舗街&ビジネス街ながら、ヨコ方向の道はピンク産業の店が林立するという不思議なエリアでした。歌舞伎町や福岡の中洲だって似たようなものか。そのタテ方向すなわちカイザー通りの中ほどに、ボナ・メンテ(Bona Mente)なる落ち着いたステーキ屋がありました。店先にドイツ語と並んで英語のメニューも掲出してあったので、肉でも食べて元気を取り戻そう! いつも西欧にやってくると、かなりの量の肉を、昼となく夜となく食べることになります。各種ステーキもありましたが、BonaMente Grilladasという品は肉類盛り合わせのようで€15.90とお値打ち。女性店員に「量は多いですか」と訊ねたら、ノーマルですとのことだったので注文しました。飲み物はグラスの赤ワインで、せっかくだから「ジャーマン・ワインはどれですか」と訊いてからそれを求めました。こちらは0.2リットルで€5.20。同じ大都会でも、ものの値段はパリよりもかなり安いですね。盛り合わせは、牛・豚・ラム・ターキー(七面鳥)4種で、ノーマルとはいえたぶん250gくらいはあったはずです。セルクルでまとめた野菜のソテー、フライドポテト、生野菜が少しついていて、見た目がきれい。おしゃれなステーキハウスで肉とワインでは、あまりドイツに来た感じはしませんが、きっとドイツ人が和風なものを求めて東京に来れば同じようなことになるでしょうね。あ、肉は普通に美味かったですよ。お店のサービスもスマートで上々。

こんなわけで、予定外つづきのフランクフルトの1日でした。ホテルに戻り、シャワーを浴びてから、0階のホテルバーに行ってみました。朝食ルームになるスペースの一角、レセプションの背後にあたる部分に小さなカウンターが設けられています。レセプションのホテルウーマンが回り込んできてホステスも務めます。ビールを頼んだら、昼間のカフェで出てきたBinding Römerが小ビンで供されました。もうこれ以上ハプニングは起こりようがないので、本を読みながらゆっくりごくごく。さらにもう1本(1本€3.00)。カウンターには先客のおばさんがいて、ホテルウーマンに何やら面倒な飲み物を注文したらしく、おねえさんは何種類かのビンを当人に見せて確認をとりつつ、大きなグラスに注ぎました。見ると、私が飲んでいるのと同じビールにスプライトを割っています。おばさん満足げに飲んでいましたけど、そんなの聞いたことないぞ! やがてケータイで話しはじめ、「ハラショー」と聞こえたので、ロシア人だったのかな。
この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。