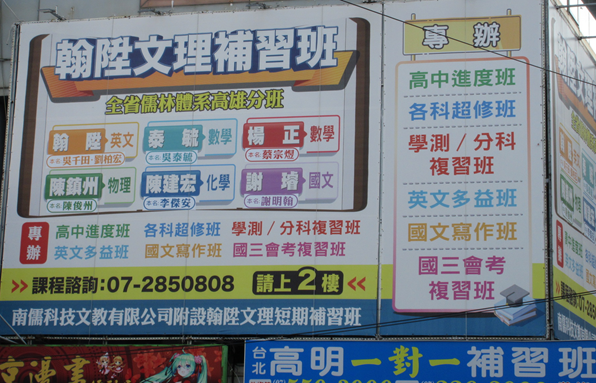古賀毅の講義サポート 2025-2026
|
Principe de l’éducation 教育原理 千葉工業大学工学部・創造工学部・情報変革科学部・未来変革科学部・情報科学部・社会システム科学部 教職課程 |
講義サポート トップ
2025(令和7)年度 教職科目における指導・評定方針
2025年11〜12月の授業予定
11月29日 近代の教育思想
12月6日 新教育思想
12月13日 日本の教育思想
12月20日 社会変動と教育
|
<来年度の教職科目>
REVIEW (12/20) ●社会がますます変化していく中で、今後はいままで以上に必要とされる能力が増えていくことを知った。私が現場に出て勤めるころには、また変化していると予測される。社会が必要とする能力をしっかりと理解し、生徒に身につけさせることをつづけられるよう、これからも学習をつづけていきたい。(応化) ●教育は社会変動と強く関係しており、従来の国民統合型で量重視の教育だけでは限界があると感じた。グローバル化やAIの時代には、多様性を包摂し、主体的に学ぶ力や協働性を育てる教育への転換が重要だと思う。(認知) ●近代公教育の成立からAI時代まで一貫して捉えることで、教育の前提が揺らいでいることがわかった。ただ、オンライン上での授業や課題が増えると、他に何かをやりながらになってしまうため、必要な知識が身につかなくなると思った。(都市) ●時代に合わせて学びの内容やそれを取り巻く環境が変わっているということを頭に入れたうえで、それに乗り遅れないような授業をつくれるようにしたい。また経済界などの要請も踏まえられるように、視野を広くもっておきたいと思った。(情工) ●デジタル化に教員が追いつけていないことでは、大学よりも小・中・高のほうが著しい。にもかかわらず小・中学生に関しては、使い方を間違える生徒に知識を教えなければいけなくなってしまった。これにより、教職課程の見直しによって、もともとあった教職課程の科目が減った。またかつての日本は国内だけを対象にしてきたが、他国に負けるようなことが増えてきたため焦るようになった。今後の生徒には、英語・コミュニケーション・デジタルのスキルが必要となった。私も変化の波に乗れるように深い知識を身につけようと考えた。(高度) ●高度情報化、AI時代など、変化が激しい中で教員になり、それをつづけることは簡単なことではないと思う。教員が「中学生/高校生だから、こういう指導をすればいい」というように勝手に境界線を引くのではなく、その生徒の未来を考えて指導したい。(認知) ●社会の変化はたしかに激しいのに、教育の変化は緩やかだなと思った。小・中学生がAIの教育を受けて理解するのは難しいと思ったし、使いこなせば楽だけど逆に興味をなくしてしまうのではないかと思った。(認知) ●社会変動によっていろいろなことが変わっているが、教育は明治5年につくられてからあまり変化していない。しかし求められているものが変わってきている。英語・コミュニケーション・デジタルとあるが、教員になるうえで、コミュニケーションとデジタルはとくに必要になると思った。AIが当たり前の時代に、生徒にどう使わせるのか、あるいはどう使わせないのかを教えられなければならないと思う。そのためにまず私自身が正しく使えるようにならなければならない。(認知) ●日本の学校教育は現代の社会変動についていくことができず、多くの課題を抱えていること、日本の子どもは英語力・コミュニケーション力・デジタル力が足りていないということがわかった。そこで完全にデジタル化を進めてしまうと、コミュニケーション力がつかなくなるなど、一度に解決できない問題が出てくる。そこをどのように解決していくかが今後問題となり、理工系の学生が動くべきなのではと考えた。(認知) ●とくに見つけようとしなくても見たい動画は流れてくるように、何を学んでおけばいいかというのは、学校の授業が教えてくれる状況では変化に対応できる人間は育ちにくいだろうと思った。一斉授業といった一定の学びを保障するための公教育の要素は、課題であると感じた。(認知)
●コロナ禍を経て、たしかに教育の本質が見えたと思う。これだけ世の中でデジタル化が進んでいるが、教育は、オンライン授業では生徒側の様子やフィードバックが難しい分野であるだろうと考えた。(高度) ●コロナ禍まではAIというものが身近になく、あまり脅威に感じていなかったが、これからもAI教師やそれに代わる何かが新しい技術によって生まれ、教員に代わる何かも出てくるだろうと考える。(高度) ●完璧なデジタル化はできないと聞いて、それこそ人間を学習するAIが実用できるようになったら、先生という職は別の形で残るのではないだろうか。AI先生もあと10年ほど経ったら普通にありそう。(応化) ●IT化といわれなくなった時代。たった5年だが、それまでにさまざまな出来事が起こりすぎた。私が中学校で支給されたタブレットは、どの授業でも使い道がなかったが、いまでは必須である。そう考えるとこの時代にいちばん適応しているのは子どもたちの側だと思った。ITの発展で自ら考える機会が減ったと感じる。これらがコミュニケーション力などのスキルに影響しているのだと思った。(応化) ●専門的なものは勉強していけばおのずと教えられるようになっていくけど、教員になったら教科の他にもさまざまなことを教えていかなければならないので、日々いろいろなことを考えていきたい。(応化) ●生徒から見れば、教師はその教科のすべてを知っている人と認識しているのだから、私がその立場になるときにその教科のエリートになっていなければいけないと思うと、ハードルが高い気がしました。この1年後期に基礎を学ぶときに手を抜かないということがいかに重要なのか、最後の最後で気づきました。(機械) ●AIが発達して教育に求められる役割が変化することがわかった。その教科の教員でも、たくさんの科目があり、一つの専門だけでなくプラス1科目をめざせるようになりたいと感じました。(機械)
●ただ単に授業に出ているだけで教員になったときに何を教えるの?といわれたときに、ドキッとしました。ただ数学・情報など専門的なものはしっかりと学習しているのですが、教職はしっかりと受けられていないのが現状なので、来年からは教員になったときをイメージしながら授業に臨みたいと思います。(情工) ●教室でガヤガヤ授業することが、いかに学びを深めることにつながるのかという内容で、私もリモート授業に比べ、教室でやる授業は何か打ち込みやすく、成長させるものがあるなと感じました。(高度) ●いまの時代はIT化ではなくICT漬け。先生の話を聞いて、ICTの授業はよいが、オンラインの授業はあまりやるべきでないと思いました。(応化) ●AI・ITの発展による教育の影響について考えると、オンライン授業が主流になるのではないかというイメージがあったが、学校に足を運び、仲間と一緒に学ぶことが大事だとわかった。しかしAI・ITをいっさい取り入れないとなれば社会に出たときについていけないという人がきっといるため、AI・ITに触れることのできる環境があるべきだと考えた。(経デ) ●SNSやAIの発達によってオンライン授業ができるようになったのはいいが、友達とのかかわりがなくなったら授業にならないというのは、とても重要なことだなと思った。友達とかかわることで学校が成り立っているんだと気づかされた。(電電) ●コロナ禍で、学校の重大な要素(人とのかかわり)に気づいてしまったことが、他にどのような物事に影響したのか。話を聞いていて、心理学の「人は何かの集団に入っていないと不安になる」というようなものに近い気がしたので、自分と周りの関係のようなものにも意識を向けなければならないと感じた。(認知)
●現代の3スキル(英語、コミュニケーション、デジタル)について、たしかに私も含めて大幅に足りていない部分があるなと思った。(高度) ●中高生のときに「ここだけやっとけばいい」と限定すると、英語を学んでも実際には使えず理解も深まらない。また科学なども表面的に覚えるのではなく、中・高でしっかりと学べば、エセ科学も見抜くことができると聞いた。たしかに私は、テスト前に軽く勉強する程度だったので、ニュースでやっていることもわからない。ネットに流れてくるものをすぐに信じてしまうので、中・高でしっかりとやっておけばよかったなと思った。(都市) ●赤の他人とコミュニケーションを取るメリットが目に見えにくいのが、コミュニケーション力が問題となる一因なのかもしれないと考えた。(高度) ●コミュニケーション力がないのは自覚しているため、大学生のあいだに身につけるべきだと考えている。自分の好きな分野のイベントなどに参加して、初めての人と話せるようになるのがいちばんよい方法ではないかと自分では思っている。(認知) ●技術の発達に教師や教育制度が追いついていないということが問題になっていますが、現在の高度情報化やAIの発達に教育が追いつき、うまく活用できるようになるのにどれくらいの時間がかかるのか気になりました。社会変動に即座に対応できるようなしくみが今後できるといいなと思いました。(経デ) ●初等教育から高等教育に向けて、だんだんと地縁的なことから、新しい人々とかかわるようにシフトしていかなければならないのだと思った。それをどうやって教育に落とし込むかを考え、新しい人々とかかわらなければいけない状況をつくり出すのがよいかと考えたが、具体案は出てこなかった。(高度) ●グローバル化が進むのにつれて、現在の教員や、今後教員になろうとする人たちが知らないようなものが増えてくると思う。さらにコロナの流行でPCが配られるなど、勉強の仕方も急激に変化したこともあり、世間の状況に合わせた授業をおこなえる教員が求められるのかなと思った。(応化) ●ほとんど構造が変わらない公教育により、量的な学びを受動的に享受するという安易なことになった結果、儀式的に得た学びと日常生活の出来事をうまくリンクできなくなったのではないか。しかし高度化していく現代社会において、教え方やかかわり方は変化したとしても、教育の目的は不変のものではないかと思う。(情工) ●主体的に学ぶことができていないのではというところに、とても共感した。現在は入試のための授業(とくに高校)のようになっており、たとえば英語なら文法を重点的に学ぶ。しかしグローバル化が進み、英語でのコミュニケーション力が求められるようになっているにもかかわらず、学びが生活につながっていないので、生活につなげられる学びを、今後していかなければならないと考える。(情工)
●「学びからの逃走」というのは、とても身に覚えがあった。大学に入ってからは「逃走」していた部分が「学び」につながっている箇所は多少感じることができるが、高校では儀式的な知識だったのだろうと思った。学びにつなげられるような教員になりたいと思った。(都市) ●テストに向けた勉強しかしない人が多数であるとあらためて思いました。私たちがしなければならないのは、教員になったら、生徒が自ら主体的に学ぶ環境づくりをしていくことだと思いました。(機械) ●私は、たしかに点数のために勉強していることが多くて、先生の仮説がとても突き刺さった。塾でバイトしているが、普段英語ができないのに宿題が全部合っていることがあり、中学1年生なのにもうAI翻訳使っているんだな〜と思って、今回の内容がピンときた。(電電) ●公教育はやはり多様性を包摂していかなければならないが、受験のような画一的な評価が残っている以上、形を変えるというのはそう簡単ではないと感じた。正解主義という固定概念に捉われず、「正解」は1つではないという考え方を浸透させていくことが大事なのかなと思った。(高度) ●いままでの学校では、教育や産業のさきがけがいたから正解主義的な教育で何とかなっていたが、これから先は学校教育と実生活とのつながりを発見していきながら、正解のない問題を常に考えていくことが重要なのではないかと思う。(認知) ●正解主義の話があったが、教員の立場として、問題に対する複数の考え方や意見を柔軟に出せるように生徒に伝えたい。(高度) ●「正解主義」と「同調圧力」の偏りからの脱却は、日本人であるからにして脱却は困難であるかもしれない。教育だけでなく社会も、この偏りから脱却するために何かリアクションを起こさなくてはならない。(機械) ●「正解主義」や「同調圧力」から脱却できる、主体的に学びに向かうことができるようになり、それを教員になって伝えられるようになれ、といわれているような感覚になった。そのような考えになってほしくてこの話をしたのか気になった。また「正解主義」などが定着してしまったいま、この考え方を変える(もしくは教える)のは、無理寄りの困難だと感じてしまったが、こう考えるのは、教員を志望する者としては、よくないのだろうか。(高度) ●で、結局どうすればいいの?と考えてしまった自分は正解主義。(認知) ●学び、学習の本質を、たびたび見失ってしまうが、今回の授業で話されていた、社会と学習を結びつけることこそが、学びの本質であるとあらためて思った。経済界の求める人材の姿というのがあるのはわかるし、それに合う人を育てることも必要だとは思うが、学校教育一般にそれを適用させて、どれくらいの子どもや先生がついていけるのだろうか? 経済界に教育が合わせに行くべきなのだろうか?と疑問に思った。古賀先生はどう思われますか? ご教授願いたいです。(認知) ●私の通っていた工業高校では、今回の授業内容とは逆に、主体的に学ぶ生徒が多かったように感じる。情報も電気も機械もすべて同じ「工業」としてくくられていることで、計算式の使い方や考え方がつながる部分が多く、その結果、主体的に学習する生徒が多くなっているのではないか。(高度)
●数式を出されたときに、私は、数式自体の意味はわかるが経済がわからないという側にいるため、経済がわかっていればこの話はもう少しおもしろくなっていただろうと思い、経済の動向にしっかり目を向けようとする気になった。(認知) ●消費性向や原発のしくみの話があったが、内容自体は高校1年レベルでも、その計算がわからなかったり理解しようとしなかったりするというのは、学びからの逃走や正解主義によるのだと聞いて、なぜその内容を勉強するのかまで意識することが重要だと思った。(高度) ●今回のたとえ話の中でいちばんわかりやすかったのは、日銀が体でいうところの心臓だという説明だ。すんなりと理解できた。(高度) ●無限等比級数を高1レベルだといっていたので、古賀先生って隠れ数学者なのではないかと考えた。(機械) ●金利のニュースの例から、テストのための勉強ではなく内容に対する理解が必要だということがとてもよくわかった。私は、金利のことはわかったが等差数列の式で少し「あれ?」となってしまったから、足りない部分があるということを自覚した。(機械)
●高度情報化やグローバル化といった社会変動の中で、学校教育が抱える課題が整理されていて、興味深かったです。とくに、これまでの工業モデルの学習が通用しなくなっているという仮説には説得力を感じました。大学という自由な学びの場に身を置いているいま、自分自身も「やらされる勉強」を脱し、自律的な学びの質をどう高めていくべきか、再確認するよい機会となりました。(都市) ●先生の仮説を見て、少し前までの日本の学校教育はキャッチアップ型で、高度経済成長期によくマッチする「指示を理解し、同じ品質で大量アウトプットする労働」であった。だが第三次産業中心の現在では、正解が必ずしも一つではない、マニュアル化が困難、対人関係・文脈理解・創造性が価値になるといった特徴がある。ゆえに今後重要になってくるのは、問いをつくる力、コミュニケーション力だと思う。(応化) ●近年、AIの発達が進んで、それに頼ることが多くなり、勉強するにもAIを使わないタイミングがなく、著作権などを意識できていない部分が作成時などに出てきてしまうので、自分で考え、それを補助してもらうという使い方を大切にしたい。そして教員になったときに、情報リテラシーやモラルを教えられるようになっておきたい。(経デ) ●学びの劣化についての話で、スポーツ選手などの英語力が例に挙げられていた。やはり「学びたい、使いたい」という気持ちをもって「自分のために」学ぶという意思があるかどうかが、スキルに大きく影響するのだと考えた。また、教育をすべてデジタルにすることには大きなデメリットと課題があり、不適切であるのに、デジタル・スキルを身につけることが学校教育の役割として求められるようになっているというのが、とても難しいと感じた。(応化) ●コロナでオンライン授業になったときは、Zoomでやっている授業を受けながら、手許では他の授業の課題をしていたりして、優先順位が変わっていました。YouTubeの動画配信のオンデマンド授業と、Zoomなどのライブ配信のオンライン授業って、どちらのほうが学力や知識を学ぶうえでよいのか気になりました。私はライブ授業のほうが、その場で質問ができるのでよいと思います。(高度)
教育原理は、同じく2S配当の教育行政学とともに、最初に教職専門性に触れる機会となる科目です。学校教育というあまりにおなじみの対象に対して、自身の経験や思いではなく、歴史的・社会的な文脈からアプローチするのがこの両科目。教育行政学が、法・制度・政策といった面から学校教育を考察するのに対し、教育原理は、教育の理念・歴史・思想を扱います。1949年に現在のような教員養成のしくみ(授業本編で紹介する「開放制教員養成」)が成立した当初からあるのは、この教育原理と教育心理学(本学では4Sに配当)だけです。教育の歴史や思想って、後ろ向きというか、もう終わってしまった過去を学ぶので、なぜこれが教職専門性の最初に来るのかよくわからないという人もいることでしょう。真の意味は学んでいく中で自ら感じ取って(体感して)いただかないとどうしようもないのですが、逆にこの部分の知識や見識が欠けてしまうと、場当たり的で根拠の薄い教育を連発するようなダメな教員になってしまうかもしれません。そもそも、いま私たちが知るような学校教育がはじまって、200年になるかどうかです。学校教育がはじまって、よかった(進歩した)と思いますか? 副作用も起こったと思うのだけど、それを上回るだけのプラスが生まれたといえるでしょうか? それは今後もずっとつづくのでしょうか? 歴史的な思考は、そうした未来へ向けての展望に直結します。 千葉工業大学の教職課程で取得できる教員免許状は、中学校と高等学校のものです。これらは教育段階でいう中等教育(secondary educaction)に属します。いま大学生であるみなさんは、初等・中等教育を経て高等教育の入口にたどり着いたところですね。では、初等教育や高等教育と比較した場合の中等教育には、どのような特長や特質があるでしょうか。また、どのような弱点や欠陥があるでしょうか。特長は生かし、弱点はそれを意識して回避すべきですね。学校教育の「中の人」になると、そうした性質を熟知したうえでの役割を求められます。中等教育は、二つの面で複雑さ、ややこしさを抱えています。一つは、そこで学ばれる(私たちを主語にするなら「教える」)内容が高度で専門的だということです。高等教育ほどではないが、かなり抽象度が高く、量もそうですが質がとにかくハード。いま一つは、そこで学びの主役となる中学生や高校生の年代というのが、発達段階でいう青年期という時期である点です。子どもでも、おとなでもないその過渡期。この青年期は、子どもやおとなと違って、まるごと把握して理解するのがきわめて難しい対象です。そんな相手に、抽象的で高度な内容を教えるのが私たちの任務ということになります。この教育原理では、中等教育の成り立ちにとくに注目して、その特長や弱点をじっくりと観察します。日本でいえば、第二次大戦後の改革の中で、初めて中等教育がすべての人に開放されました。それまでは「中等教育は任意なので、受けたい人だけどうぞ」だったのです。なぜその時期に中等教育がすべての人に開放されたのか。それは「よい結果」だけをもたらしたのか。歴史の中から、そうした重要なものをすくい上げていってください。 当科目のもうひとつの重要な内容が教育の思想です。教育は人類につきものですし、誰もが学校教育を(児童・生徒として)受けていますので、理想の教育とか、教育の問題点というものに対する意見を各自それなりにもっているのではないでしょうか。しかし主観や経験だけから導かれる教育観は、しばしばハイリスクなものです。独りよがりで、およそ自分以外には通用しない論理なのかもしれません。学校教育がはじまってから現在までのあいだに、無数の人が経験した教育の中から特徴的な要素や側面を取り出し、適切な言葉で表現した教育思想は、私たちの教育観を立体的で「使える」ものに鍛え上げてくれます。いずれも典型的な文系のアプローチですので、理系のみなさんにはちょっと面食らうところもあるのでしょうが、教育者をめざすのであれば避けては通れない思考法といえます。ゆえに、大半の教職科目に先立って、この科目が設定されているのだとお考えください。
|