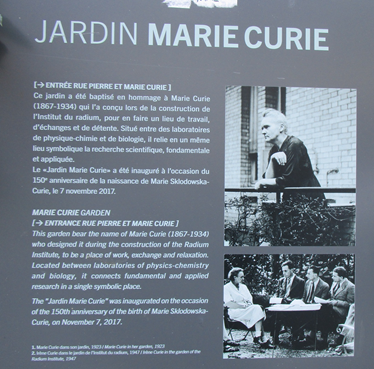古賀毅の講義サポート 2025-2026
|
Études sur la
société contemporaine I: Pour vivre dans une société du futur proche 現代社会論I:近未来の社会を(に)生きる構想と探究
|
講義サポート トップ
現代社会論II:グローバル思考と近未来の世界への学び
2025年11〜12月の授業予定
<第3部 現代社会と文化・教育>
10月10日・17日 ジェンダー問題と格闘してみる
11月7日・21日 新仕様の学校教育
12月5日 高等教育(大学)の遊び方
|
本年度の授業は終了しました。 REVIEW (12/5) ■学びたい人たちが学んでいた中世の大学から、産業の発展や国家を強化する必要に伴って学問分野が整理された近代の高等教育が誕生するという成り立ちを知ることができて、有意義でした。高校の段階で好きなことを好きなように学ぶ時間が確保しやすく、そのまま大学に進学してさらに学びを深めることのできる附属高校は、自ら学ぶのに適した環境だと感じました。卒業論文があることにより、研究の仕方を学ぶことができるというのも附属校の特色だとあらためて思いました。 ■今回は、大学という場所がどのように生まれ、時代に合わせてどのように変わってきたのかを学んだ。とくに印象に残ったのは、大学の役割が、貴族のための学びの場→国家のための人材育成の場→誰もが進学できる場所 と大きく変わってきたという点である。大学は昔から一つの形のまま存在してきたのではなく、その時々の社会の変化に合わせて姿を変えてきたことを知り、学ぶ場としての大学をあらためて見直すきっかけとなった。そして先生も触れていたとおり、こうした変化がいまの就職活動や働き方の変化ともつながっていると思う。最近では、企業が人を採用するときに「大卒」という肩書だけを重視するのではなく、「その人がどんな力をもっているか」「何を学んできたのか」をより大切にするようになってきている。IT企業などではとくにその傾向が強く、大学名よりも実際にできることや経験が重視されるケースが増えているようである。情報が、誰もが受け取れるものになった一方で、私たちが何を信じどう判断するのかという「学ぶ姿勢」がより重要になっていることは、大学教育の現代的な課題とよく似ていると感じた。授業では、大学生には「自分で学ぶ内容を選び、必要なら分野を変えるくらいの主体性が必要」と述べられていたが、SNSの世界でも同じように自分で情報を選び取り、正しく判断する力が求められる。今回の授業を通して、大学の歴史を知る音は、単に教育制度の変化を理解するというだけでなく、私たちが生きている社会そのものを考えるヒントになると感じた。大学もSNSも「誰でも参加できる時代」になったからこそ、自分で選んで自分で考える力を大切にしたいと思う。 ■エリート大学のマス化、ユニヴァーサル・アクセス化の時代を迎える→社会全体のモラトリアム化 という流れがあった。18歳時点の入学試験の結果が就職で重視されてしまうからこそ、質の高い教育をおこなうはずの大学が十分に機能しない。これは経済成長が停まっているいまだからこそ見直すべきでは。消費社会化、資本主義化の進展に伴い、大学のあり方も大きく変化してきた。かつて学問は上流階級のものだったが、現在では経済成長や国力強化のための手段という側面が強くなっている。大学が就職実績を掲げて受験生を集めようとするのは、はたして純粋な学問といえるのか、資本主義のための実利的なものなのか。とにかく、学問も大学も変化していることがわかった。 ■いままで受けてきた教育の歴史について詳しく知ることができて、非常に興味深かった。教育の根底の考え方としては、学びたいことを学ぶべきだということであり、そのような心持ちで学ぶからこそ自身の中で発展させ、国家等の共同体の中で自分なりの学びを発揮することができる。しかし時代が進むにつれて国家を強化するための教育へと変化していく。そのような教育は国家の政治体制などによって変化し、本当に必要性のある学びができるとはいいがたい。そして近代に入り、実用的かどうかにとどまらず、人格を耕し土台としての教養をはぐくむための教育が重視されるようになった。この学びは前述の2つの学びの中間をとったようなもので、自分の好みにも国家の方向にも偏らず、自分の中でも国家の中でも応用可能な学びを身につけることができるのである。またユニヴァーサル化という段階において、学歴社会が崩壊してきたという話題が非常に印象に残った。大学進学、その後の発展した学びが一般的になっている現在、学歴に頼らずとも自身の強みを示すことができるような、新たな学びの入口を見つけたいと考えた。 ■もともとはエリートが自由に学ぶのを目的につくられた大学だけど、女子大生ブームのころからレジャーランド化したという話が印象的だった。学ぶことが目的なのではなく就職のための猶予の場のようになっているということも印象に残っていて、学びたくても学べなかった人がたくさんいて、それが自由に学べるようになって、その結果がそうなのだということもわかって、考えさせられた。 ■グーテンベルクの活版印刷の発明は、よいことばかりかと思っていたが、大学にとっては「知の独占」の崩壊につながったというところに驚いた。大学といっても、生い立ちの違いなどがあり一種類に括るのは難しいと思った。 ■高等教育は昔から(11世紀から)存在していたにもかかわらず、いままでその歴史を考えたことはありませんでした。だからこそ今回の授業はある意味新鮮に感じました。ナポレオン、グーテンベルクなど知っている歴史とつながっていたことに驚きました。 ■西洋における高等教育が、初等・中等教育よりも早く成立したこと、そしてそれが元来は成人による純粋な知の探究を目的とした、自律的な共同体であったということはとても興味深かった。ナポレオンがつくった高等教育機関や、プロイセンが国家再建のために創設したベルリン大学が、人材育成を目的とする現存の大学の標準となった経緯もよくわかった。 ■大学の起源が、「学びたい人が学びたいことを学びたいように学ぶ」ところにあったという歴史を学ぶことができた。学部歴を重視する人も周りにはいて、それに違和感を覚えたことがあったが、やはり学部歴などという考え方は間違っていて、そのようなことを気にするよりかは自分が本当に学びたいことを扱っている学部に行くべきだと思った。 ■欧州の昔を描いたアニメなどを見ていると、大学が神聖な場所として扱われていたり、神学という学びの分野があったりして、少し不思議に思うことがありました。これを、就職のためでなく学ぶための大学であったと捉えると、アニメで描かれていた大学の尊さに納得がいきました。「学びたい人が学びたいことを学びたいだけ学びたいように学ぶ」ことによって、「好きなこと」を見つけて「好きなように」学ぶことができる。これは早大本庄高等学院の強みの一つであると考えます。高校→大学→社会へと視野を広げていく学びを目標にします。
■上位学歴の取得が地位の上昇に直結したのは明治と戦後の2回だけだったということに驚いた。学歴によって社会に出ては入れる会社が決まるから勉強しなさいと親にいわれつづけて、とても違和感をもっていたが、今回の授業を受けて、そんなことはもう変わっていっていることがわかった。このまま大学に行っても、自分で問題を解決するような力が身につくような気がしないので、せっかく大学に行くならスキルを得られるようにがんばりたいと思った。 ■流れがあるから文学部よりも法学部のほうが「役に立つ」と思われている、というのは怖いと感じました。知らず知らずのうちに自分の行きたい学部が操作されているかもしれない、とあらためて進路を振り返りました。いままで「学歴社会」というのを勘違いしていたかもしれません。会社の成長をめざして、より高い能力をもつ人材を雇おうとしたときにより高い学歴をもつ人材を雇うことになる、ということなのだと知りました。高学歴の人がただ有利になるということだけではなかったのだと理解しました。私も正直「学歴」が欲しくて早稲田に入ったというところはあります。社会でやっていくには、そんなものは関係なしに、自分自身の学びをしていくことが重要なのだと思いました。 ■今回のテーマはまさに自分たちについて扱われていて、なんともレビューを書きにくいが、高校の授業という入口を通して、なんとなく自分の興味・関心を見つけ、深める機会に恵まれた3年間ではあったと思う。行きたい学部は決まっていますが、これからも学びの手法をアップデートし、学びつづけられるようにがんばります。 ■誰でも高校・大学に行く時代であるが、周りに流され、時代に流され、動機もなしに学校に入る人が大勢いる中で、お金がある人だけが行ってやりたいことができるというひと昔前のものよりも、学びのモチベーションが下がっていると思う。そのため、そのレベルに見合った教育の仕方に変えていく必要があるのではないかと考えさせられた。大学に入る人が増えたことで学歴社会が完成し、有名大学・有名企業にいる人がすごいとされる風潮ができた。この風潮が全然なくなっていない現在では、ネームバリューは少なからず、一定の意味はもっていると思う。 ■附属高校に入ったことで中3のときに大学を決めてしまっているので、大学に行くのが当たり前だと感じていた。なぜ、なんのために大学で学ぶのかを見つめなおす必要があると思った。社会では依然として、日本は学歴社会だといわれることもあるけれど、どのような学歴であるかよりもその人自体がどうあるのかのほうが重要だとわかった。 ■大学に行くのが当たり前となっている現代の大学の捉え方(心構え的なもの)を少し知ることができた。西洋中世史の授業で大学の登場について学んだことがあったので理解しやすく、現代の日本の大学観が異質であると感じた。大卒の肩書の質が低下している状況では、ただ大学に通うのではなく、いかに主体的に専門分野を学ぶかということが重要なのだと認識させられた。 ■私が大学にもつイメージは、やはり就職のためというものが大きい。しかし今回の授業で「学びを究める」という意味の大学を再認識することができた。だからこそ大学での学びは社会への第一歩として捉えることができた。 ■大学はカリキュラム内で就職の支援をするわけではないから「就職予備校」ではない、という話がありましたが、企業のインターン参加を理由に大学の授業を休むことを認めないという授業がある、という話をSNSで見かけたことがあります。大学の対応は正しいと思います。企業が就職活動を早期化させる動きに対して何か対策を取らなければ、大学生の負担が大きくなってしまうのではないかと思いました。 ■大学には就職に関するカリキュラムがないのにもかかわらず、就職に関するサポートが手厚いなどといって学生を集めるようになっているところがおもしろいと思った。大学の集客は、偏差値・知名度よりも就職に関するものが大切であると思った。 ■現代社会において学問や就職が一つの産業になっており、それがいまの学歴社会をつくってきたといえることがわかった。大学に入るうえで、大学という外面だけでなく自分自身の内面も磨く必要があり、その準備段階である1〜3月にかけて、私はできるだけ本を読み、思考し、自分の頭の中で整理する能力を身につけていこうと思った。 ■かつては文学部がトップだったけれど、いまでは就職に不利などといわれるようになってしまったという話があったが、社会全体としての雰囲気と、自分は何をするのかという意思決定は切り離して考えていくべきだと思った。 ■早稲田大学の一般入試の倍率が上がっているのは、指定校推薦の枠を他の高校にあげすぎているからだと考えた。学歴に関して、その1回の結果だけで人の能力を評価するのは安直だと考える。ただ、ひとつの参考とするのは間違っていないと考えた。 ■大学のユニヴァーサル・アクセス化によって高等教育が万人に開かれ、誰もが教育を受けられる・学べる環境の整備がなされているものの、学ぶ環境が量的に増えたことで動機のない層が増えているとあった。少子化が進む現代では「なんとなく」という感覚で入学する人がさらに増えてしまうのではないかと思った。インターネットや娯楽漬けになりがちな現代において、自ら学びを見出したり考察したりすることが貴重な経験であると思った。 ■1990年代に大学生が取り上げられているドラマが流行したという話があった。その時期は若者といえば大学生、という考え方だったと知りましたが、現在の私のイメージは、高校生が若者ということも強いので、消費を求める対象が徐々に若くなっていき、さまざまな人に消費を促しているのだなと思った。
■私も「大学に入ることが目的になっている人々」のうちの一人なので、今回の授業からは大きな印象を受けた。とりあえずよい企業に就職するというのを最終的に目標にして、なんとなく課題をこなしてきたけれど、それでは産業に呑み込まれるだけで中身が空っぽだなと思うようになった。一方で、大学(とくに私立?)やそこまでの教育が産業の一環であることには疑問が残る。AIが登場して人間の存在意義を一人ひとりが認識しなければ生きる価値がなくなってきているのだから、学の先に自由がある、ということをもっと早くから気づいておきたかった。 ■正直、私自身も早稲田の附属校を受験した最も大きな理由は、早稲田大学というブランドに魅了されたからである。もちろんこのブランドは就職面だけで形成されているものでもないが、今回の授業を聞くと、私も単純すぎる理由で入学してきたのかなと思った。しかしこの3年間で、幅広い人間関係や附属校ならではの経験をたくさんできたので、今後の4年間ではさらに多くの面で自分を磨いていきたい。 ■企業において年功序列があり、年を重ねれば地位が上昇するというしくみに疑問を感じていたが、企業の規模自体が大きくなっていくという理由に納得した。学歴フィルターについて、第一次の書類審査においては学歴がかなり影響すると思うので、まだ機能していると感じた。 ■企業に入社するときに、この企業にどれくらい役立つことができるのかを判断する面接があるが、○○大学出身=能力が身についている というように認識されることは、学歴を資格のように捉えていることだと思った。そして、いまではパソコンのスキルや高度な内容の業務に適用できるかどうかが入社後に問われる。大学名という、大学入学時の肩書やそこにいた経験だけでは対応しきれないように思う。企業にとって「役立つ」人材は、具体的なスキルを求められている場合には、学歴ではなく資格や詳細な経験を重視するべきではないか。 ■私は近ごろ頻繁に「大学に行って何したい? 将来の夢は?」と質問されますが、いざ考えてみると自分でもどのような理由で大学に行こうとしているのか、そもそも大学に行く決断をしたのは自分が「行きたかった」からなのか「行かないといけない」という使命感を抱いたからなのか、という疑問を抱くことが多いです。最近では、卒業した大学という「学歴」を重視するよりも、個々人の素質を見極めることを重視する流れになってきていると思いますが、私は学歴を含め、頭のよさで人々をある程度判断することは理にかなっていると思います。入学試験が難しい大学は、そのぶん大学で学ぶ内容が難しく専門的であると思いますが、であるとすると出身大学は個人の専門分野における知識の深さや専門性を表していると考えられ、したがって、ある企業や担当者が人材を選ぶときは、ある分野により特化している「高学歴」に惹かれるというのはごく自然なことだと思います。また対人関係においても、あくまでも私は、自分と同等かそれ以上の知識量のある、あるいは頭のよさをもっている人と関係を築き、コミュニケーションを通して学びたいと思うので、もし目の前にいわゆる「低学歴」や「Fラン大学出身」の人と高学歴の人がいるなら、間違いなく高学歴の人のほうに意識せずとも惹かれると思います。また「学歴」は、個々人の努力の量や忍耐力を見る指標にもなると思っており、単純な「頭のよさ」を示すもの以上の価値があると個人的に思います。 ■有名大学を卒業することは就職に有利であるとよく聞きますが、それは産業がつくり出した要素も強いということを、授業を通して感じた。授業スライド内で働き手を採用する際の目的と手段が逆転しているとあったように、学歴の捉え方が変化してきているのだと考えた。 ■学歴社会ではなくなった、ということには賛成ですが、そうであるなら、いまはどのような観点で優秀な人を見極めればいいと思いますか。また、私個人の意見としては、学歴+α社会になったと思いました。
■私の偏見かもしれないが、現代人よりも昔の人のほうが、学習意欲が高かったのではないかと感じる。授業スライドにもあったように、かつての大学は「学びたい人が学びたいことを学ぶ場所」であり、そこには明確な意思をもつ人しかいなかった。対して現代はよくも悪くも学習環境が整いすぎていて、物心ついたときからなんとなく勉強をやらされているという感覚の人が多い。個人的な思い出だが、小学生の学習意欲の向上のためか、小学校では勉強している=えらい という風潮があって、とくに受験組は受験しない人たちを見下すような雰囲気が感じられた。そんなことを考えながらも私は結局、中学校・高校を受験していて、正直勉強よりも受検することが目的になっていたという自覚がある。志望校を選ぶ際にも偏差値や学校のブランドしか考えず、本当に自身で湧いた興味の勉強をしたことがない。だからこそ、先生がいっていた、高校まで目的なく勉強してきた人は大学に入ってからもできない、という言葉がすごく刺さった。大学に行って何を学びたいか考えておらず学部選択を迫られている、まさに私のような人に向けられた言葉なのだと思う。これから自分の考えを変える、なんてこともできないと思うので、深く考えずに、選択してきたことが間違いじゃなかったと信じて生きていきたい。 ■高等教育のための準備として上から下に向かって中等教育が生まれ、一方で初等教育から上に向かって中等教育が生まれて、統一されていまの中等教育になったというのがすごく興味深いです。また開放制に興味をもちました。学びたい分野は別にあるけれど、その分野を学んだうえで教職に就いて子どもに経験の機会を与えるきっかけをつくりたいなと考えているからです。最後におっしゃっていた、AIのように教科を教えるだけの存在の危険さは、教科に分けることができないような事柄に対する考え方がはぐくまれない、ということが挙げられるのかなと考えました。 ■中等教育の成り立ちがおもしろかった。初等教育からできたタイプと、高等教育からできたタイプの2種類があるというのが新鮮だった。また高等教育の本質は、目的やねらいがあるというより「学びたい」欲が根底にあるという話も興味深かった。以前、古典を学ぶ意味・目的がわからないと思っていたが、高校でも高等教育的な学びが提供されているのかと思った。実学を意識しすぎている自分は、大学でしっかり学べるのか危機感を覚えた。 ■専門的なアプローチや処理が、大卒ならではの能力であり、それを学問以外の仕事に生かさなければいけないといわれていたが、自分にはまったくそのイメージが湧かず危機感を覚えた。また、大学生になって急に「好きなこと」を「好きなように」学べるわけではないと聞いて、では世の中の人は入学前にいつそのすべを知るのか疑問に思った。 ■両親の世代は商業高校から大手銀行に就職したが、いまなら高卒では難しい。そう考えると、3〜40年でかなり学歴に対する価値が変わっているなと思った。私は理工学部への進学を考えているが、8割以上の学生が大学院まで進学していて、資格取得で就職に強いという点ではよいが、私自身は20代後半になっても学生をやっていることに違和感を覚えている。地元の友人と会ったとき、進路の話になり、「先生になる」「看護の学校に行く」などと周囲がいう中で、「稼げる仕事をする」というように明確な考えがない自分は、せっかく早稲田の附属に進学したのにむしろ甘えた考えや、将来に対して未熟な意見しかもてない人になってしまったなと思う。その反面、選択科目の多さや受験を前提としない授業内容などを3年間受けてきて、おそらくこの高校でしか身につけられない部分を手に入れたと思う。
■今回は、単なる知識の習得にとどまらず大学での学び方や生き方そのものについて考えさせられた。とくに、学際的な学びに対する、広く浅く薄くなるのが必然といった指摘は、安易な選択に流されそうになる学生の姿勢を戒めるものであり、自分の適性や動機を真剣に見つめなおす重要性を痛感した。またキャリアや専攻を固定的に捉える必要はなく、学びつづける中で見えてくるものを重視すべきだという、柔軟な視点を得ることができたように思う。 ■高校生活を振り返ると、ただ授業を受けていただけで、さらに自主的に学んだことはなかったことに気づきました。そもそも授業を受けていれば十分だと思っていたので、大学生活に向けて、考えを改めます。 ■高校の時点ですでに「自身での学び」が本体になっているというのは、3年間を通じてひしひしと感じていたことだったが、自分から進んでおこなおうとしたことはなかった。経験がなかったのでハードルが高いものだと思っていたのである。しかし、だからこそそれを深める作業を1年間かけてさせてくれた卒論は、とても貴重で、大変だがいままでに経験したことのない楽しさを与えてくれるものだった。大学ではこの「楽しさ」をより得られる方向に向かいたいと思った。 ■授業内で先生がおっしゃっていた、なんのために大学に行くのかという言葉は、耳が痛いなという感じでした。私は自分でアパレルブランドを経営したいという夢があり、そのために一流のコンサル企業に入ってコンサルを学びたい、そのためには一流大学に入らなければ、よい学部に入らなければと思っていました。でも先生の言葉を聞いたときに、「大学で」という点に関してはなんの興味も関心もなかったことに気づきました。学部選択前に、本当にこの学部は、私が興味のあるものなのか、深く学べる分野なのかということを一度立ち止まって考えておきたいと思いました。またジェンダーの壁についても触れられていましたが、大学生活を通して、そんなことでは揺らがない、男性にも負けない、自信をもっていえる絶対的な何かを身につけるために大学に行こうと思います。 ■君たちはなんのために大学に行くの?と授業内で問われたとき、たしかに「ただ行くべき場所だと思うから」と答えるしかありませんでした。有名大学に行くからといって自身が他社より勝っているとは思わないけれど、就職に有利という観点からは、無意識のうちに有名大学に行きたいとどこかで思っていたのかもしれません。これから学歴よりも実力が重視されるようになる中で、自分には何があるのかを客観的に考えなければならないと感じました。まだ学部を決めていないので、自分が「学びたい」という意思のもと、たくさん吟味して選びたいです。いろいろ試して必要であれば方向転換もして、好きなように、自由に自身の学びを深めたいと、今回の授業で強く感じました。 ■先生が教育学に畑を変えたきっかけについてもう少し詳しく教えていただきたいです。 ■私が大学に入ることで何がやりたいのか、何をすべきなのかを再度見つめなおすことができた。この科目の受講を通して社会学的なことを学び、社会への考察の仕方を見ることができたのはとてもおもしろかったし、一学生、ひとりの社会の構成員としての自身に、自覚的になることができたように思う。大学に入る意義は学問を究めることであるが、同時に、大学を有意義に活用するためにも学問・知が必要なのだろうなと思った。2、3月をただの休みにしてはいけないと気を引き締めることができた。 ■うまくいけば大学進学が近づいている中で、今回の授業は、大学に行く目的・動機がない状態がつづいていたら、ということを考えさせられました。中学校のころから将来を見据えなければならないという教育を受けてきて、でも正直学びたいことはないし、将来の夢はとくにないし、よいところに就職したいから進学したいという気持ちが大きく、ダメなのかなと思っていました。でも授業を通して、大学が知識習得のための単純な空間ではなく、自分を知って将来の方向性を探究する場所であることがなんとなくわかり、学びの質を上げていきたいと思いました。 ■私は、ずっと楽をして生きようと思ってきたけど、3年生になって興味のある分野を学んでみようと思い、ためしに苦手な社会科の現代社会論Iを選択しました。先生がおっしゃっていたとおり、学ぶためには知識が必要で、先生やSide-Bの友人が何をいっているのかわからないことも多かったけれど、自分で選んだ科目だったので、がんばって受講したつもりです。たくさんの知識を得られてすごく楽しかったですし、自分のためにもなりました。
現代社会論は、附属高校ならではの多彩な選択科目のひとつであり、高大接続を意識して、高等学校段階での学びを一歩先に進め、大学でのより深い学びへとつなげることをめざす教育活動の一環として設定されています。当科目(2016年度以降は2クラス編成)は、教科としては公民に属しますが、実際にはより広く、文系(人文・社会系)のほぼ全体を視野に入れつつ、小・中・高これまでの学びの成果をある対象へと焦点化するという、おそらくみなさんがあまり経験したことのない趣旨の科目です。したがって、公共、倫理、政治・経済はもちろんのこと、地理歴史科に属する各科目、そして国語、英語、芸術、家庭、保健体育、情報、理科あたりも視野に入れています。1年弱で到達できる範囲やレベルは限られていますけれども、担当者としては、一生学びつづけるうえでのスタート台くらいは提供したいなという気持ちでいます。教科や科目というのはあくまで学ぶ側や教える側の都合で設定した、暫定的かつ仮の区分にすぎません。つながりや広がりを面倒くさがらずに探究することで、文系の学びのおもしろさを体験してみてください。 当科目は毎年、内容・構成とサブタイトルを変えています。2025年度は近未来の社会を(に)生きる構想と探究です。副題の妙なところに(かっこ)がついていますが、助詞を入れ替えると「生きる」の主語も替わるようになっています。どのようになるかは、各自でお考えください。現代社会論Iではこのところずっと探究(re-search)を掲げています。これは文部科学省も強調するところであり、日本の児童・生徒、とくに中高生が重点的におこなうべきだと考えられている知的プロセスにほかなりません。インターネットに加えて生成AIも身近になりましたので、○○の意味はなんですかといったシンプルな問いであれば、一瞬で答えを出せてしまいます。下手な先生が講釈するよりもはるかに平易でわかりやすいですよね。しかし、社会で生きて、生活・生産に携わろうとするときに、それで済むのかということについては、絶えず自問してほしい。実際に直面するのは、まだ出会ったことのない問題や、正解がはっきりしない課題であることが多いのです。○○の意味というような知識を、高校や大学でしこたま取り込んだとしても、社会のほうがどんどん変わってしまいますので、せっかくインプットしたものがたちまち無駄・無用になります。構想や探究というのは、その先で持続可能なもの、というイメージで設定した当科目の主題です。現代社会がいま抱えている問題の多くは、原因や構造がはっきりしているが解決策が見出しがたい、あるいは解決策をめぐって対立が起きているという場合と、原因や構造すら明らかでないというものです。正解を覚えてテストで出力し、点数を取るという方式にはなじまない、そうした部分こそ、小・中・高と社会科や地理歴史、公民科を学んできた先の部分、つまりみなさん自身がその力を磨いていくべき部分ではないかと、私は考えています。大変ですし面倒ですが、この作業はとてつもなくおもしろい。大変だけどおもしろい、ということをわかってしまうと、もう探究をやめられなくなります。生涯にわたって学びつづけることになります。その一歩にしたいですね。 2つのことをあらかじめ心得てほしい。(1)これは政治、こっちは経済、それから世界史、日本史、倫理、あるいは数学、理科、情報・・・ などと、学校の都合で設定されたような教科や科目の枠組にしばられるのは、もうやめましょう。何もいいことはありません。大学受験生であれば入試で選択する科目を重点的に学習しなければならないのでしょうが、附属のみなさんはその点でアドバンテージをもっています。世の中に教科の境目なんて存在しません。苦手でも不得意でもいいから、飛び越えましょう。(2)難解なこと、意味のわかりにくいことがあっても、絶対に思考を停めない。もっと易しくなりませんかとか、もっと高校生に身近な話題にしませんかといわれることもあるけれど、社会というのはそんなに甘くないし、高校3年生のアタマの水準や興味に向こうから寄り添ってくるということは絶対にありません。こちらが、寄せていかなければ。学期終わりまでに点数を取れるようになりなさいというわけではなく、ひとまず、とりあえず思考しなさい、食らいついてでも考えなさいというだけなので、それを早めに放棄してしまうのはもったいないです。率直にいって、高校3年にもなれば人によって出来・不出来やアウトプットの程度の優劣はかなりあります。あったっていいじゃないですか。メジャーリーグも草野球も野球です。それぞれの場所でバットを振ることに意味があります。 |