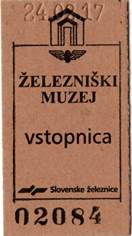|
山の上はテーブル状になっていて、そこにお城(grad)が建てられています。とはいっても天守閣のようなものがあるはずはなく、こちらの城というのは土台部分が重要で、上ものは普通の居館に近いものです。もともと12世紀に軍事設備として構築され、歴代の支配者によって重要拠点として重視されてきました。現在では公共の公園のような位置づけになっています。いろいろな展示やカフェなどもありますが、ともかく展望台ならぬ展望搭の上に登ってみたい。
 国旗のはためいているところが展望搭 国旗のはためいているところが展望搭
 
居館にすぎないと申しましたが、見張り台のような直方体の搭があって、そのてっぺん(屋上)が吹きさらしの展望台になっているようです。矢印に従って進んだら、途中で係の人に止められました。「この先は入場料がかかります」とのこと。ケーブルカーの運賃とは別のようで、あらためて€7.50を徴収されました。あとで見れば、ケーブルカー往復と展望搭のセット料金が€10とあったのでそうしていればよかった。ケーブルカー乗りたさに、表示をしっかり見ていなかったようです。まあいいか。
お城のフラットな部分には大勢の市民やヴィジターが憩っていたのに、有料のためか、展望搭エリアには人の姿がほとんどありません。周囲を頑丈な鉄柵で囲ったらせん階段をぐるぐる回って登ります。本来はなかったはずのガラスで採光窓を覆っているため、直方体の内部に風は入ってきません。途中に展望室があるもののスルーして、さらに登ります。リュブリャナの標高(標準値)が海抜295m、この展望搭のてっぺんは同400mとのこと。登りきったところは当然ながら四角形の小さな屋上で、360度のパノラマを楽しむことができます。風がかなりありますが、行くぞ。

リュブリャナの中心部が眼下に(写真中央にプレシェーレン広場とフランシスコ会教会が見える)
 
 
わ〜本当にいい眺め。川沿いの低地に広がるリュブリャナの全体像がよくわかります。リュブリャニツァ川に沿ってカーブを描く、赤い屋根の旧市街がまた美しい。もう滞在3日目で、町の主だったところをほとんど歩いてきたため、それらをおさらいするような感じで俯瞰できるのがいいですね。私このところ各種の授業で、知識や言語能力を獲得することで「ちょっと高いところに登るとそれだけ視野が広がるじゃない。そういう感じで学びを深めてほしいんだよね」ということを力説するのですが、こうしてときおり自分が高いところに登って俯瞰する経験を積んでいるのでそういう喩えになるのかもしれないですね。吉野源三郎の名著『君たちはどう生きるか』(1937年)では、主人公がデパートの屋上から下界を眺めてそこに「社会」を発見するという象徴的な場面が冒頭にあります。しかし実際には、「町の絵」にすぎないものを「社会」に変換するにはやっぱり知的なコンバータが必要で、ITに頼ってばかりの生活ではなかなか身につかないことではあります。ともかくも若い人たちはどんどんあちこちに出かけて、高いところに登ってみてみなさいって。
というお説教をしたい相手は教え子たちではなく、屋上にいる他の2人。20歳くらいの背の高いカップルで、眺望そっちのけで濃厚なラブシーンを続行中(笑)。お金払って階段をぐるぐる登ってきてまでするようなことかね。バカじゃないのかと日本語でつぶやいてみたけど気に留めることもなく、ずっとなさっていました。バカじゃないのかね。
 
リュブリャナ城を見上げる (左)大聖堂越しに (右)三本橋から
 
川沿いの遊歩道 黄昏どきにはひときわ美しい景観になります
お城からの眺めを堪能して、これでひとわたりリュブリャナで見たいところを見ることができました。14時半ころホテルに戻って休憩。何しろ市街地が狭いので、市内交通というのをまったく利用していません。ことごとく徒歩で過ごせてしまいます。この日も早めの夕食でいいかなと考えて17時ころ再起動します。いいレストランないかなというので、休憩中に(よせばいいのに)トリップアドバイザーなどで情報を検索。いい店というよりは、レストランがありそうな地区はないかなというのが本命です。というのも、旧市街のスターリ広場界隈は昨夜利用しましたし、といって周辺部には脈がありません。たいていの都市では町なかというより、少し外れた住宅街みたいなところにいいレストランがあるほうが普通なのです。リュブリャナは、カフェのたぐいは目立つけれどレストランは少ないような印象。すると、リュブリャニツァ川をもう少し上流側に進んだところにいくつかお店の情報が記されています。「地球の歩き方」の地図の範囲外やね。ないならないでいいから、町歩きのつづきで行ってみることにしよう。
日の沈みかけた町を、すっかりおなじみになった三本橋→スターリ広場のルートで南(上流側)に進み、また対岸に戻ってしばらく歩きました。なるほど、リュブリャニツァ川に別の小さな川(Gradascica)が流れ込む付近に5、6軒の飲食店が並んでいて、それなりの雰囲気を醸し出しています。ただ、何となくこちらのセンスとは違うんだよね。で、その地区はやめて、中心部にゆっくり戻りました。何となればまた旧市街に行けばいいと思いながら歩くうち、ふと思い出したのが、初日に駅からホテルに向かう途中で見たお店。ホテルのすぐ並びみたいなところにあり、来てみてもいいなと思ったのにその後は忘れていたのでした。本当にいい店かどうかはわからないけど、いつもいうように、飲食店選びなどまあそんなものです。外れを怖がってネット情報にかく乱されるのがいちばんまずい。
 
 
Gostilna Šesticaというその店は、スロヴェンスカ通り側から入るとずいぶん奥行きのある広いフロアを有しています。初老のおじさん店員がずいぶんと明るいトーンで招き込み、テーブルに案内してくれました。バインダーに綴じられた分厚いメニューは写真つきで、あまり見かけない料理も多いようです。逆に迷うなあ。とりビー(とりあえずビール)を飲みながらじっくり検討しよう。料理を考えるので先にドラフト・ビアをくださいというと、おじさんは「よっしゃ、スロヴェニアのユニオンをもってくるよ!」とまたまたハイトーン。燃料を入れてもなかなか決めきれないところを察したおじさんは、日替わりメニューらしい豚肉の何ちゃらという料理を熱心に勧めてきました。ポークの発音が完全に巻き舌になって、ポルルクみたいになっています。それはスロヴェニアン・ディッシュですかと訊ねると、にこりと笑って、イエースと。ではそれにしましょう。ただ、明日には東京に向けて帰らなければならないので、最後のディナーは少し色をつけたい。ザグレブと同じように、前菜にスープ(dnevna juha / Soup of the Day)も発注します。
このスープがじわじわ美味しい。タマネギ、ニンジン、ラルドン(ベーコンに似た豚肉の燻製)、パセリ、ナメコのつぼみみたいな3mmくらいのキノコが入ったコンソメで、フランスで食べるオニオン・グラタン・スープの土台みたいな味わいです。0.5Lの生ビールがさっさと空いてしまったので、グラスの赤ワインをといったら、「イエスOK、ワン・モア・ビア」と誤った解釈をされかけてしまいました。当方の発音が悪いのもあるのでしょうが、これまで英語圏を含む欧州各地でone glass of red wineという音声を発しており、そんなに間違えようもないと思うけど。会話していてわかったのは、おじさんは首都のど真ん中の飲食店で働いているためサービスに必要な英語は心得ていますが、あまり複雑な表現はしないし、発音もけっこうガタガタです。おそらく社会主義時代に育ってまともな英語教育を受けていない世代なのでしょう。ややあって運ばれたのは、ワン・グラスではなく小ピッチャー(0.25L フランスでいうpetit
pichet)。まあこれは望むところだ(笑)。しかもワインが美味しい! おじさんが「あなたは英語のほかに何語を話しますか?」と訊ねるので、フランス語を話す旨を告げると、これまた知るかぎりのフランス語でリュブリャナ最高、赤ワイン美味しいみたいな内容を声にしていました。サービス精神に敬意を表して、上手にフランス語を話されるのでびっくりしました、とフランス語でいったらにこりと笑いました。

メインはSvinjska ribica
izpod pekeという料理名。後刻グーグルで翻訳してみると、豚肉のパン仕立てとでもいうような意味らしい。肉とパン生地を巻き込んでオーヴンでローストしたものらしく、バタークリームソースが添えられています。豚肉の皮がしっとりして、肉本体との歯ごたえの違いがあって美味しい。豚肉の皮って中華の東坡肉に欠かせない部分ですが日本ではなかなか食べないですよね。つけ合わせはキャベツのパイ、実に軽い食感でこちらも美味しい。素材からいえば広島のお好み焼きみたいなものか。肉とパン生地を巻き込んだものはチェコのプラハでも食べたことがあり、中欧各地にこのような料理があるのでしょう。真にスロヴェニア料理なのかどうかは存じませんが、フランスあたりではあまりお目にかからないものなので満足しました。お皿を下げにきたおじさん店員は、「シュトゥルーデル?」と訊ねます。ウィーンのアップルパイ、アプフェル・シュトゥルーデルをデザートに勧めているようです。ノンノン(笑)。エスプレッソをもらって仕上げました。勘定は、メイン€16、スープ€3.50、ビール€2.90、ワイン€3.50、エスプレッソ€1.50で〆て€27.40。少しばかり心づけ置いていきましょう。
最終日の2月24日(金)は、ゆっくり朝食をとって荷物を整理し、10時にチェックアウト。この日はリュブリャナ空港を18時15分に出発する便に乗り、フランクフルトで羽田行きのANAに乗り継ぐ行程です。まだまだ昼の時間が使えます。空港は昨日訪れたクラーニュに近いところにあり、バスで40分程度とのことですが、アクセス・バスの乗り場は国鉄駅前のターミナルでホテルからはやや遠い。ザグレブでは駅前にもってこいよと文句をいったのに勝手なことです。ガイドブックにはプライベート・バスなる情報が載っており、ネットで検索してみると、Languna Shuttleなるバンのような乗合自動車が€9で主要ホテルまで迎えにくるということです。この価格ならばいうことはないし、めずらしいタイプの輸送手段なので興味もあります。そんなわけで前日の昼に、ホテルのレセプションに予約を頼みました。シャトルは1時間半に1本程度の運行で、スロンはもちろん「主要ホテル」なので特約があります。18時の便ですといったら、ホテルマンが15時25分のシャトルを勧めたのでそれに従いましょう。3泊ぶんの宿泊料はカードで事前決済されており、チェックアウトに際しては、初日のレストランでの飲食代、ミニバー(冷蔵庫)の飲み物代と、このシャトルの料金をまとめて支払いました。シャトル料金は運転手に現金で支払ってもよいとのことですが面倒なのでまとめました。どのホテルマンもきびきびしていて行き届いており、水がお湯になるのが遅いのをのぞけば部屋も上々で、いうことがありません。当たりのホテルでよかったです。褒めたついでにキャリーバッグを午後まで預かってもらいました。
 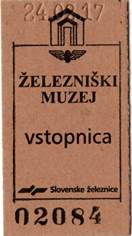
 
蒸気機関車が静態保存されている鉄道博物館 右はナローゲージ用SL
ガイドブックの地図には中心部からかなり外れたところに鉄道博物館(Železniški muzej)の文字が見えます。マニアとしてはのぞかない手はありません。スロヴェンスカ通りをまっすぐ北に歩き、国鉄線のガードをくぐった先の住宅街の中に所在。妙なところにあると思うものの、おそらくはかつての機関庫を転用しているので、線路の真横というロケーションなのでしょう。エントランスが地味すぎて手前であきらめてしまう人もいるかもしれない(笑)。それこそ昭和のローカル線の駅舎みたいな小さな建物が受付でした。入場料€3.50を支払うと、係りの女性がなつかしい「硬券」をなつかしい切符ホルダーから取り出して渡してくれます。――わあ、この装置なつかしいですね。私が子どものころ、こういうのありました! 「この機械に興味をもたれる方がけっこういらっしゃいますよ(笑)」
鉄道の博物館と銘打っていますが実態は蒸気機関車(SL)限定です。十数両の機関車が静態保存されていて、その建物はまさに機関庫でした。1969年生まれの私でももうSL世代ではありません(国鉄の定期運用は1975年の北海道が最後)。SLそのものをなつかしく思うことはなくて、歴史的な遺物としていつも見ています。鉄道趣味の中でもSLというのはちょっと特殊なところがあり、クラシック・カーを愛する人と似ていて、人間がつくり出した様式美や機能美に惹かれることが多いのではないでしょうか。歴史好きの乗り物マニアである私から見ても、近代そのものというか、産業革命が煙を吐いて疾走しているようなイメージなんですよね。オーストリア・ハンガリー帝国はかなり早い段階で鉄道技術を英国から導入し、内陸に広がる広大な領土を面的に結ぶことに注力しました。大帝国とはいえ海への出口はアドリア海にわずかにあるだけなので、トリエステ(現イタリア領)やダルマティアなどとオーストリアやハンガリーの本土を結ぶ路線は重視されたのでしょう。となるとリュブリャナなどはまさに要衝だったはずです。
 
(左)転車台の跡 背後の旧機関庫の中にSLが展示されている (右)保存状態がよくない機関車も
ちょっとマニアックなところですが、動輪の寸法と、ロッド(シリンダーと動輪を結ぶ棒状の装置)の配置などがボディよりも興味深い。蒸気機関車の原理からして、シリンダーの威力がでかければ機関車としてのパワーが大きくなるということなのだけど、力強さをとれば速度にセーブがかかるし、車体が頑丈すぎると重量が大きくなって路盤に負荷をかけるしで、バランスをとるのが設計者のセンスでした。主力幹線で活躍したであろう機関車を見ると、たしかによくできています。日本のC62型によく似た配置。小回りの利くタンク車(石炭と水を積む部分を機関車本体と分離していないタイプで、小型のため大きな動力を必要としないローカル線で用いられる)はC56っぽい。ナローゲージ(762mm軌間)用のコンパクトなSLも展示されていました。山岳路線などで使われたのかな? ――などと、SL世代ではないとかいいながらけっこう萌える(汗)。機関庫の外にも静態保存のSLがいくつか展示されていますが全体に保存状態がよくありません。この博物館はスロヴェニア国鉄が運営しているようだけれど、酸素(資金)注入が足りないのか、盛り上げるための努力がいまいち。国・都市の規模が小さいので鉄道趣味人口自体がさほどでないのかもしれませんが、やるならもう少しちゃんとやったほうがいい気がします。まあでもおもしろかった。
持ち時間があと3時間ほどなので、さすがにもうどこかを見学することもなく、最後に三本橋とリュブリャニツァ川を見ておこう。これほど1ヵ所で長く過ごしたのは、パリ以外では久しぶりです。帰国したら週明けからさっそくお仕事満載なので、中欧の静かな町の空気をいまのうちに存分に吸っておくことにします。最終日は小雨交じりで、折り傘を開くかどうかというところ。ここまで雨天がなかったのはありがたいですね。
 
 
この日もランチは見送り。この日もというか、欧州→日本の移動は時差の関係で「いま何時」がぐちゃぐちゃになるため、飲み食いの定時性に意味がなくなります。フランクフルトを20時45分に出るANA羽田行きでは、西欧標準時の21時半くらいにどっしりした食事が供されるはずで、ハーゲンダッツの(カチカチに凍った)アイスを舐めたらすぐ消灯されお休みを強要されるに違いありません。国際線に慣れないころは飲み食いのコントロールがうまくできなかったな〜。
15時前にホテルに戻り、預けていた荷物を引き取ってロビーで待機。すると15時10分ころホテルマンと中年男性(運転手)が並んで現れ、「ミスター・コガですね。お車の用意ができましたのであちらへ」と案内しました。25分の予定だけどずいぶん早いですね。ホテル前に横づけされたのは白いバンで、これだと最大6人くらい乗れるのかな? ホテル・スロンから同道するのは1人でしたが、町はずれのビジネスホテルみたいなところに寄って、バッグパックの若い男性を1人拾い、そこから空港に向かいました。途中までは前日クラーニュからの帰りに通った道と同じです。雨が強くなってきましたが、これ以降はずっと屋根の下だろうから問題なし。最近、空港〜ホテル間でタクシーを利用したケースが2度あり、マルタは€20(クリスマス当日の割増料金で本来は€15)、ラトヴィアのリーガでは€15の定額チケットを購入しています。市内からリュブリャナ空港までの距離は両空港よりありそうなので、乗合タクシーのような設定で€9ならばかなりお得な感じがする。
 空港シャトルがホテルまで迎えにきた 空港シャトルがホテルまで迎えにきた
リュブリャナ空港(Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)はスロヴェニアの基幹空港ですが、国の規模に見合ってかなりコンパクト。ザグレブ空港といい勝負でしょう。クロアチアほど国土の広がりもないため、スロヴェニア国内の空港は他にマリボルにあるくらいです。地域によってはクロアチア、オーストリア、イタリアなどの空港を利用するほうが便利だったりします。シェンゲン協定の関係で、リュブリャナ→フランクフルトはいわば国内線扱いになり、何時間も前にチェックインしておく必要もないのですが、外国では何が起きても不思議ではないので余裕はもっておきたい。16時ちょっと前に空港に到着し、小さなカウンターにキャリーバッグを預け入れると、あとは時間つぶしになります。予想外だったのは、ちゃんとしたレストランが非制限エリア、制限エリアのどちらにもなかったこと。ここでがっつり食べておけば時間もとるし、夜半の変な時間に○○い機内食で腹を満たさなくて済むと思っていたのに、当てが外れました。そういえば欧州屈指のハブ空港として機能するヘルシンキ・ヴァンター空港もそんな感じでした。日本の地方空港も軽食堂がせいぜいというところが多く、それで十分だと普通は考えるのかな。
 
 リュブリャナ空港 リュブリャナ空港
チェックイン・カウンターのすぐ並びに保安検査場があるのも日本の地方空港に似ています。1フロア上に出発ロビーがあり、そこはわりに広々としていて、お子さま用の遊具スペースまで設けられていました。座る場所がないほど混雑していましたが、チューリヒ(スイス)、プラハ(チェコ)、ワルシャワ(ポーランド)、ミュンヘン(ドイツ)、ウィーン(オーストリア)、ブリュッセル(ベルギー)、ポトゴリツァ(モンテネグロ)と、17時10分までの出発便への搭乗が終わるとがらんとします。そのあとはわが18時15分のフランクフルト行き、19時55分のイスタンブール行きなどが飛ぶだけで、基本的に夜間運用はしていない模様。出発ロビーの一方の端に設けられているゲートは出国審査場で、シェンゲン圏外に向かう便に搭乗する際にはパスポート・コントロールがおこなわれます。当方はもちろんその対象外。上記でいうとポトゴリツァとイスタンブールだけがシェンゲン圏外です。不思議なもので、長いことパリを中心に動いていると、同じシェンゲン圏とかユーロ圏というだけで「地続き」のように思えてきますね。そうだからこそ低賃金の労働者もテロリストも容易に移動できるのだといえばそうですが、どこをどのように仕切ったところでそうした事案は起こりえます。問題は、国家という枠組で長いこと取り組んできた社会政策とか治安対策といった事柄をEUレベルで十分に果たせるのかという点でしょう。率直にいって、まだまだ不十分ですし、地域により温度差があります。
旧ユーゴスラヴィア構成国のクロアチアとスロヴェニアは、EU内では「後輩」の「小国」で、経済規模も影響力もさほどに大きくはありません。ただこの両国、そして加盟候補国であるセルビア、モンテネグロ、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国(この国名は歴史的にギリシアのものだと加盟国のギリシアおよびキプロスが強硬に主張しているためEUはthe former
Yugoslav Republic of Macedoniaの呼称を暫定的に使用。日本政府も同様の立場)は、欧州統合が加速していった1990年代に、それとは相反するような苛酷な状況を経験しました。とかく書生論とか理想論とか夢想とか、エリートの作文だなどといわれがちな欧州統合において、そうした経験を経た人々が「それでも自分たちはEUに加入して欧州の仲間になる」と表明していることはきわめて重要です。彼らの経験が欧州に真の強さをもたらすことを願わずにはいられません。

アドリア航空のCRJ900機に乗って東京(羽田)へ帰ろう(フランクフルト空港にて)
アドリア航空(Adria Airways この英語の社名がスロヴェニア国内でも用いられている)はスロヴェニアの国営航空会社です。スロヴェニアの国土がアドリア海に接している部分は20kmくらいのものなんですけどね。いまどき国営?という気もするけれど、旧ユーゴスラヴィア時代は組合主義を体現して、スロヴェニアの人々が協同企業として運営する民間企業だったのが、戦争・独立を経て経営が悪化し、1996年に国営化されるという欧州ではあまり例のない経過をたどりました。現在はルフトハンザやANAなどと同じスターアライアンス加盟社となっています。このため東京〜リュブリャナ間はフランクフルト乗り継ぎのいわば最短ルートで行くことができます。それはいいのだけれど、このJP124便はフランクフルト着が19時35分で、乗り継ぎ時間が70分しかありません。同一アライアンスだと便利すぎて、ときどきこのような旅程になります。案の定というか、わが便の出発が遅れますというアナウンスが流れました。機材の整備不良などがあると困るので簡単に飛ばしてもらうわけにもいきませんが、乗り継ぎの都合があるんだよな。ま、先方に責任のある話ですのでANAが発券した以上は乗り遅れても別便に振り替えてくれるのは間違いありませんから、焦ることはありません。ボンバルディアの小型ジェットは結局20時ちょうどに着陸しました。それも、巨大空港のずいぶん外れのほうに(笑)。連絡バスで建物内に入ったところにANAの係員がいて、東京羽田行きのお客様はこちらへと搭乗者名簿のチェック。乗せてもらえるのはありがたいけど、けっこう走らされました。最近はシャルル・ド・ゴール空港よりもなじみがあるターミナルなので道に迷うことはありませんが、何しろでかい空港ですからね! そうだ、ここでシェンゲン圏を出るので出国(出欧)審査があるんだった。こういうときに限って、いつもなら黙ってスタンプを押す審査官がくだらんおしゃべりをしてきます。日本のパスポートを手にするや、「ジャパン? ミスター・アベ」と謎の発言。プライム・ミニスター(首相)のこと?と聞き返すと、Yes, he is a good man.と内容もどうしようもない。その発言を打ち消すのと、それどころじゃないから早く通せという意味を込めてノーノ―といったら、「ユーは彼のことが嫌いなのか?」と。オフコースなんだけど、そんなこといって出国(出欧)させてもらえないのも困るので、早く旅券をよこせというポーズで応えました。俺は貴国の首相(アンゲラ・メルケル)のファンだとは、もちろんいいませんでした(笑)。余計な運動をさせられたぶん、機内で飲み干すサッポロビールがひときわ美味しかったことはいうまでもありません。いつの間にか私は南スラヴの国々からはるか遠ざかって、北極圏のほうに向かっています。
南スラヴの優美な姉妹 おわり
西欧あちらこちら にもどる
|