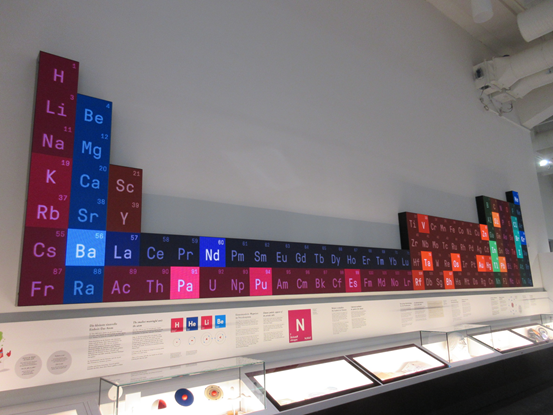古賀毅の講義サポート 2025-2026
|
Études sur la société contemporaine 現代社会論
|
2025年7月の授業予定
7月1日 新たなヒューマン・ビジネス
7月8日 産業・労働のグローバル化
7月15日 変わりゆく産業社会とキャリア形成
|
本年度の授業は終了しました。 REVIEW (7/15) ●やりたいことができるのでこの大学に進んだが、それが将来の仕事にしたいものかと聞かれると悩んでしまうことがある。この授業を受けて、まだ新しいものを見つける機会があると知ったので、学びの姿勢を崩さずに、将来やりたいことを見つけたい。 ●当然のことをもう一度見直しつつ、視野を広げられる、よい授業でした。社会が不安定だから自分の心も不安定でいっぱいなのだと思っていたが、学校でぬくぬくしていて外の世界を見つめていなかっただけなのかもしれないと思った。 ●終身雇用の時代から雇用が流動化する時代に変わっているので、これからが大変だなと感じた。また、在学中にスキルアップにつながる資格を取っておきたいと思った。 ●社会の形が目まぐるしく変化する中で、いままでの雇用のあり方も見直す必要があると思った。 ●雇用環境の変動についてよくわかった。専門性をしっかり身につけていけるように勉学に取り組んでいきたいです。 ●大卒だからといって仕事ができるとはかぎらないというのをあらためて感じた。将来のためにも、いまできることをしっかりやって、大学での学びを深めていきたい。 ●終身雇用や年功制が崩壊しつつあるのは理解できるのですが、崩壊したらどのような雇用方法になるのでしょうか? ●戦後から高度経済成長期あたりのような、誰にも能力と努力が求められる時代が来たのかもしれない、と考えた。 ●あと5〜10年ほどで、日本最大の労働層が引退して、雇用が大きく変わる一方で、アメリカのように新卒の雇用機会が減ることになるのではないかと考えますが、今後の日本の雇用はどうなっていくと思いますか? ●終身雇用の流れが変わっていることで、これからは個人の能力によって職を手に入れるかどうかになっていくことを知り、常に情報収集やスキルアップが必要だと思ったが、これだけ聞くと自分が社会で生きていけるかが不安になる。
●大学院の修士課程に進もうと思っていて、修士卒となると社会人になるのが2年遅くなる。「職」への意識が育ちにくいといわれているが、研究していく中で常に働いている自分の姿を意識しながら過ごしたい。 ●生涯学習時代のキャリア形成において、たしかに社会人になってから大学に入りなおしたり分野を変えて学びなおしたりすることで、より深い内容まで考えながら学ぶよい機会になると思うが、お金に余裕がないとできないなと思った。 ●社会の変化や働き方について考えるきっかけになった。大学院進学も選択肢の一つとして意識するようになった。これからは専門性だけでなく、自分で考え、動く力も大事だと感じた。 ●シャイな性格の人が増えていることなど、近年になって変化する人間の性質が、社会や産業の形を変えていると思った。雇用流動化の時代は、学力や知識よりも人間性に重点が置かれると思うので、大学生活で、人とのかかわりや経験を積むことが重要であると感じた。 ●これからもさまざまな人と交流し、自分の専門外のことを聞き、知識を身につけていきたいと思いました。 ●現代は、自身が得た能力を常に更新し、考えながら過ごさなければ、この流動的な社会に呑み込まれる危険性がある。おそらくこれからの社会は、専門性がある人にとっては過ごしやすく、逆にそれがない人には生活しづらくなると思われる。 ●雇用流動化が進む中、新たな技術を学んだ後輩たちに後れを取らないように努めようと思った。 ●最後にあった「いままでこうだったから今後もそうだ、という助言を過信しない」という言葉が印象的で、柔軟に物事を捉える視点が大切だと思った。大学選びや学部選びも、「就職のため」だけでなく、「自分がどう生きたいか」を考える材料になると思った。 ●一般論や仮想現実、狭い世界ばかりを見てきたが、社会には自分の生きている世界と異なる側面や例外がたくさんあることを知ったうえで、いまの自分の視野を広げたり、さまざまな人と交流したりすることが、将来の自分のためになるし、これからの時代の変化を追う動体視力を養うことにつながるのではないかと思った。
REVIEW (7/8) ●世界や日本でいま何が起きているのかを知らないと、損をしていくのは私たち自身だと気づいて、大学生のうちに勉強しておかないと痛い目を見ると思いました。 ●グローバル化で仕事の仕方や働く場所がどう変わるのかがよくわかった。ニュースで見ていたことがつながって、身近に感じられた。 ●グローバル化にはいろいろなメリットがある一方で、進め方によっては社会にデメリットが生じる可能性があることがわかりました。 ●日本に住んでいるので日本だけグローバル化しているのだと思っていたが、世界中でグローバル化が進んでいるのだと理解した。 ●グローバル化を強く推し進める傾向にあるが、あまり妄信しないようにしたい。グローバル化によって大企業の無国籍化が進んでしまうことで、産業の空洞化も進み、そのまま国家の衰退につながってしまうのだろうか。 ●最近『コンテナ物語』(マルク・レビンソン)を読み進めているのですが、今回のファーストリテイリングの発展や世界各国の発展の内容(グローバル化)がリンクして、非常によかったです。 ●グローバル化が進むにつれて各国間での競争が激しくなり、その影響はとくに中小企業で大きかったのではと思った。 ●自分が使っている製品やサービスも世界中とつながっていることに驚いた。また、スポーツ選手の移籍も経済や産業のグローバル化と関係があることが意外だった。 ●グローバル化についての先生の定義で「国境が低くなる」という表現がおもしろいと思った。日本の経済はもうよくならないのですか? ●グローバル化は世界とつながりやすい分、他国への依存性が高くなるので、他国の情勢が国内経済に影響を及ぼしやすいと思う。単純にグローバル化を進めることはよくないと思いました。
●日本でグローバル化が進んでいる、進んでいないことと、その理由を教えてください。 ●グローバル化と第三次産業の国際課には強い関連があると思っていたので、1990年代に日本経済がグローバル化したころに、産業の高次化も同時に進んでいたのではないか。 ●トランプさんは、日本を含めて世界中に関税かけまくってアメリカの赤字直そうとしていますが、どこかやり方が過激だと思います。他にもロシアの肩をもったりするなど、どこか偏ってしまっている。一歩間違えればアメリカの信用ガタ落ちになるとは思いますが、わざとやっているのか、何かの思惑があるのか疑問です。 ●中国に産業技術が追い抜かれてしまったのは、政治的要因もあるのか? 研究費不足などといった問題もあるように感じました。 ●円安のいま、非正規を正規雇用に切り替えたり、技能実習生の待遇をよくしたりすることは、長い目で見ると困難である。一見すると非正規のほうが勝手がいいように見えるが、実際は将来的に大きな代償を払わされることがわかった。 ●抜け穴として、外国人労働者を日本で働かせているが、コンビニで24時間働かせることができるのはよいと思う。また店員が外国人だったらクレームも少ない気がする。 ●グローバル化によって、外国人が技能実習生として多く日本に来るようになった。しかし犯罪を起こす人もいるため、否定的な意見をもつ人も多くいる。こうした問題をどう解決するかが課題だと思う。 ●海外へのボーダーが上がれば円高になるのでしょうか。私は海外に行ったことがないので、お金を貯めて、円高になったら行きたいと思います。先生は海外に行ってよかったと思うものはありますか? ●日本の円安がとてつもなくなっていることを利用して、海外でバイトしたらどれくらいの収入になるのかが気になった。また非正規労働と正規労働の違いを踏まえ、将来自分が正規雇用してもらえるよう専門性を高めるとともに、就活に向けて自分の夢を探すための知識も集めておく必要を感じた。 ●授業を聞いて、いま日本で稼いでいる人たちが外国に流出することが多くなっているという話をよく理解できた。もうすぐ20歳になるので、年金やらを払わなければいけないのがつらい。 ●年金や解雇リスク等の着眼点はいままで意識しなかったが、話を聞いて、正社員がよいことをしっかりと理解できた。 ●起業するにしても相当なリスクがあるけど、正社員であれば国民年金を納めていたら厚生年金をもらえて将来は安定している。それだったら若い人の大半が正社員になろうという思考が多くなるのだと、私の中で納得しました。 ●最近、日本人ファーストという考え方が大きくなっていますが、資源などがあまりない日本にとってはあまりよくないと思いますが、どうでしょうか。 ●グローバル化で外国や外国人が身近になったが、日本でも文化の違いなどから摩擦が激しくなりはじめた気がする。SNS上では人種差別やジェノサイド肯定の過激な発言も見られて、とても残念で、怒りの気持ちがある。日本に来るなら日本のルールやマナー、文化は尊重して守ってほしいとは思うが、守っていない外国人ばかりではなく、民族全体をひとくくりにし(主語を大きくし)、さらに差別するというのは間違っている。これから共生について考えていきたい。 この現代社会論は、学部指定科目群1に属し、「人間・社会の理解」にかかわる分野として設定されています。現代社会というのは「世の中すべて」のように広い範囲を指しますので、なかなか捉えどころが難しいのですが、当クラスは産業(industry)に注目して、社会の成り立ちや近年の変化、そして近未来の可能性や課題などを考察していきます。みなさんは小・中・高の社会科や公民科で、第○次産業といった話を何度も扱ってきたことでしょう。また地理の授業では「この地域の産業の特色は」といった切り口で学ぶことがしばしばあります。大学の教養科目では、もう「試験のためにおぼえる」などという(ほとんど無意味な)ことはありませんので、授業で扱われている内容を常に自身に引きつけて、「自分たちの問題」なのだという視点で考えましょう。最もわかりやすい話としては、「数年後、大学を卒業してどこかに就職する」人が大半であるはずで、その「どこか」の話だということです。冷静に考えればわかるように、世の中は常に動いていて停まることがありません。「いま」の様態がずっとつづくはずがない。ですから「いま、いちばんイケてる産業はどこですか? 僕そこに就職します」という発想は、10年後、20年後になると話の前提自体が変わっていて、当人が損するということになるわけです。私(古賀)は、長年にわたって高校・大学で社会系の授業をもっていますが、そこで学んでいる「社会」が、自身の立っている足場であり、これから生きていく舞台なのだという感覚をもたないままでいる生徒・学生がずいぶん多いな、もったいないなと思うことがあります。せっかく学ぶのであれば、「社会の有意義な見方」を身につけたいですよね。 科目名についている「現代(の)」は、英語ではcontemporaryです。接頭辞のcon- は「共に」という意味であり、tempoは時間を意味するラテン語由来の語です。つまりは「同時代の」「時間を同じくする」という形容詞が、社会にかかっていることになります。同時代の、というのは、どの範囲なのでしょうか。20歳になるかならないかのみなさんにとって、それは「ここ数年」なのでしょう。スマートフォンが日本で普及したのが2011年ころからなのですが、それ以前の社会は「相当に古い時代」に思えるのではないでしょうか。しかし、当科目で捉えようとする「同時代の(現代の)社会」は、だいたい50〜80年くらい、テーマによっては100年くらいにもなります。これから何十年か先を見通すには、それくらいの幅をもって、社会を捉える必要があります。受講生の中には、進みたい産業分野がすでに固まっているという人もあるだろうし、まるで見当がつかないという人もあることでしょう。いずれにしても、「この分野には興味がないから、今回はパス」などと安易に考えずに、いったん自分の頭で考えて、問題をかみしめるようにしてみましょう。どんな分野に進むにしても、商売する相手は別の分野の人ですし、市場のニーズを知ろうとするなら狭い範囲に閉じこもっていてはどうにもなりません。商品開発に携わろうとすればなおさらです。たとえば、農業(第一次産業)のことは視野の外だという人が多いことでしょう。でも、農業で用いられる機械は製造業のうち機械工業(第二次産業)でつくられるものですし、農作物が流通するしくみはサービス業(第三次産業)に属します。どの分野でもそれ単体で成り立つということはありません。これから先の時代は、さらにそうした相互関係が重要になります。 <評価> |