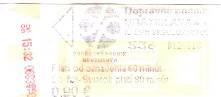Vers
les capitales de Habsbourg…
|
|
PART7 ドナウの流れとともに |
|
変な押し売りガイドで肝心の教会の印象が薄れてしまったのは残念でしたが、ブラチスラヴァの景観や歴史の跡を探訪できて満足しました。予定していたよりも早いけど、これからぼちぼち中央駅(Bratislava hlavná stanica)のほうへ向かいますかね。16時前後の列車に乗れば17時台にウィーンに着くでしょうから、それからお土産を買って晩ごはん・・・でちょうどいい塩梅。日本人にも、このところどこでも見かける中国人にも出会いませんでしたが、思った以上に「観光客」がたくさんいて、町もそれを歓迎していることがわかりました。私のような日帰り客はいいですが、何日か滞在してお金を落とさせようとするなら、もう少し仕掛けが要るかもしれない。スロヴァキアの田舎もおもしろそうだけど、やはりハンガリーのブダペストとのセットが現実的かね。
大統領官邸の前に電停とバス停があり、かなりの路線が集まってきています。トラムとバスのほかにトロリーバス(無軌条鉄道 架線から集電して走るバス)も走っていますね。バス運賃は15分まで€0.70、60分まで€0.90と距離やゾーンではなく乗車時間で区切られています。地図を見るかぎり15分もかからないと思うけれど、まあ大した差額でもないので余裕をもって€0.90にしておくか。停留所の横に3台ほど券売機があり、日本のバスの「整理券」と同じサイズ、紙質の切符が出てきました。裏面に、スロヴァキア語・英語・ドイツ語の注意書きがあり、乗車後ただちに切符を刻印機に通してマークしなければなりませんと読めます。こういう作法は場所ごとに違うので、そのつど確認するほかありません。現金の場合、紙幣を使用できるケースは多くないので、何にだって対応してしまう日本の交通機関に慣れてしまっている人は要注意。
それにしても、駅舎の外観やその周辺も含めたしつらえは、昭和の地方都市の駅そのもの。私が子どものころの旅行では、駅舎を出たあたりに旅館の送迎車が何台もいて、ハッピを着た兄さんが大きな荷物を車まで運んでくれるということが方々でおこなわれていました。客待ちのタクシー運転手が退屈そうにタバコをふかしているところも往時の感じだなあ。温泉旅館の看板広告でもあれば日本映画のロケにだって使えそうな風情ではあります。
窓口でウィーンへの片道切符を頼みました。€13とのことで、€30の船はやっぱり観光料金だったんですね。欧州の鉄道の切符は基本的に同じフォーマットで供されます。乗車時間は1時間程度ですが「国際列車」ですので、スロヴァキア語とドイツ語の表記が並んでいました。ウィーン側のターミナルはどこなのかな、たぶんミッテ駅だろうと思っていたら、中央駅(Hauptbahnhof)なんですね。まだ造りかけと聞いていたのだけど、供用開始されているのか。これも首都圏ではほとんど見なくなった、黒地にオレンジの文字で示す電光掲示板を見ると、ウィーン行きは出たばかりで次は40分後。ごちゃごちゃしたコンコースにいてもおもしろくないなと思って駅前に出て、見上げると、1階(日本式でいえば2階)部分のテラスにカフェらしきものがあります。行ってみると、団体客だってさばけそうなテーブル席が並ぶ、これも古典的な「駅内食堂」でした。そこには人影がなく、おやつタイムのこの時間帯のお客はみんなテラスにいるようです。何とも無愛想な兄さんがメニューをもってきたので、開く前にドラフト・ビアと注文しました。向かい側のテーブルにいるのは、受験生なのか問題集にかりかり書き込んでいる息子と、いちいちちょっかいを出して指導する母親。スロヴァキアからハンガリーにかけてはワインが優勢ですが、ドイツと地続きですのでビールも普通に飲まれていると予想します。斜め前のテーブルにいたカップルも大ジョッキを豪快に空けていました。うん、普通のピルスナーで、普通に美味い。 ぼちぼちホームに行くべき時間になったので、勘定を頼もうと声をかけても、兄さんはなかなかやってきません。他のテーブルに呼ばれたり、料理を運んだりで忙しいのはわかるけど、優先順位がおかしくなっています。2度ほど声をかけて効果がなかったので、面倒になって直接レジに行って会計してもらいました。日本ではそれが普通なんですけどね。スロヴァキア語?でぺらぺらと数字をいわれたのでレジスターの表示を見たら、€0.81だって! 首都の中央駅構内でこんなに安いんじゃ、多少の無愛想もがまんしないといけませんね(笑)。天国やな。
ブラチスラヴァはウィーンにほど近く、その距離はわずか60キロメートルに過ぎません。ウィーンとブラチスラヴァは、国の首都としては世界で最も近距離にある2都市であり、すでに第一次世界大戦前には電車で結ばれていました。ブラチスラヴァは、かつて「ウィーンの郊外」とも呼ばれ、その豊かな歴史は、ウィーンの歴史とも重なっています。このような事情から、町の人々は、戦争や共産主義の時代以前から多言語を話し、現在でもスロヴァキア語のほかにドイツ語やハンガリー語を話す人々がいます。再建が進み、かつての輝きを取り戻しつつあるこのスロヴァキアの首都には、今日もなおウィーンと似たノスタルジックな雰囲気があります。しかしながら、今や過去の歴史や文化遺産の共通性以上に両都市を結びつけているのは、未来の可能性です。ブラチスラヴァは、将来ウィーンとともに、新生ヨーロッパの中で最も反映する地域を形成するだろうと考えられているからです。(『ブラチスラヴァ 絵入りガイド』、pp.3-4) 長く地方都市の1つにすぎなかったものの、いきなり首都に昇格したことだし、ごく近いところに世界的な都もあることだし、この際ウィーンと1つの都市圏を形成して、統合欧州の中でも求心力のある地域にしたいという願望が表れていますね。それはウィーンにとっても望ましいことに違いありません。いまのところはブラチスラヴァからの片思いであったとしても。(なお「国の首都として世界で最も近距離にある2都市」は、アフリカ中部のコンゴ川下流をはさんで向かい合う、コンゴ共和国のブラザヴィルとコンゴ民主共和国のキンシャサというのがおそらく正しい。近いところで2kmくらいです)
第一次大戦の戦後処理は、二重帝国の解体を前提に進みました。1920年のトリアノン条約(ヴェルサイユ宮殿の庭園内にある離宮、大トリアノンで調印された)は、ハンガリーと連合国との講和条約ですが、このときハンガリーは現在のような「小国」サイズに転落しました。250年にわたって首都を置くほどだったスロヴァキアは、ハンガリーから引き離され、独立ではなくチェコとの合同という運命をたどることになります。
ウィーン中央駅は、かつての南駅を壊して、その跡地を利用するかたちで建設中の新しいターミナル。以前は方面別だったターミナルを1ヵ所に統合するという、ベルリン同様の構想によるものです。これまで訪れた主なところでも、ロンドン、パリ、リジュボーア(リスボン)には中央駅がなく、方面別になっています。東京だってそうですよ(東京・上野・新宿 かつて房総方面行きは両国をターミナルにしていました)。南駅の拡充ではなく取り壊して造りなおすことにしたのは、配線の問題に加えて、駅舎などの規模が機能に対して小さすぎたからでしょう。降り立ったホームは真新しくぴかぴか。ただ、まだ2面4線しか供用しておらず、コンコースを含めて残りの大部分は建設途中でした。この程度の状態でよく使うものではあります。駅前もがたがたで、Uバーンやトラムを直結させる工事も未完成のため、かなり歩かされました。中央駅駅からUバーン1系統で3駅、都心ど真ん中のシュテファンプラッツまでやってきました。
ま、しかし、予定どおりビールのアテとしては最高で、小ジョッキをおかわりしてもりもり食べました。日ごろ量を食べないのであっぷあっぷに近い状態です。2杯目を小にしたのは、酔っ払いそうだからではなく、胃袋のスペースの問題。ビールは一時的にスペース使いますからね! 料理が€14.50、サラダ€3.50、中ジョッキ€3.80、小ジョッキ€2.90で、〆て€24.70。前夜に比べればかなり安上がりで、おそらくこのへんが欧州で夜の外食をする際の標準でしょうね。土曜の夜にパリに着いてから7日目の夜になります。初日から、ウサギ、牛、ムール貝、仔羊、マス、仔牛、今宵のマルチ肉と、たんぱく質を摂取しつづけた1週間でした。メイン食材を日々変えているのはもちろん意図的なことです。今回もよく食ったなあ。欧州最後の夜なので、部屋で小休止してから、ホテルバーでワインを2杯飲んで仕上げました。この日はW杯欧州予選が各地でおこなわれており、バーのテレビではドイツ代表vsオーストリア代表の一戦を流しています。画面に食いついている客と、無関心なのか外国人なのか本を読んでいる客がいて、おもしろい。残念ながらオーストリアは敗れました。
この付近(ウィーン市内)のドナウ川は細長い中洲をはさんで2流に分かれています。都心側が本流、反対側がノイエ・ドナウ川(Neue Donau 新ドナウ川)。ノイエ・ドナウ川は、1970年代に掘削された本当に新しい放水路で、あいだに生まれた中洲がドナウ島(Donauinsel)ということです。この島の地下部分には透水できるところもあるらしく、水質の浄化にも役立っているらしい。
|
この作品(文と写真)の著作権は 古賀 毅 に帰属します。